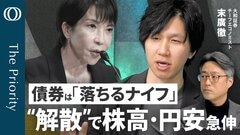終戦直後の混乱の中、中国に取り残された日本の子どもたちがいました。中国と、日本。二つの祖国を持つ彼らが今、伝えたいこととは。
戦後の混乱の中、家族と離れ離れに...「中国残留孤児」とは
9月10日。中国東北部にある黒竜江省ハルビン市の空港にひとりの男性の姿がありました。宇都宮孝良さん(82)です。
宇都宮孝良さん
「5年ぶりに来ることができてとてもうれしいです。家に帰ってきたような気持ちがします」

宇都宮さんは中国で育ったいわゆる「残留孤児」です。今回、残留孤児の仲間や家族など約90人とともに中国を訪れました。空港には中国側の支援者が「お帰りなさい」の旗をもって、彼らを歓迎しました。
宇都宮孝良さん
「私は40年以上、中国で養父母に育てられ、幸せな日々を過ごしました。養父母に大切に育ててもらったことは、一生忘れません」

1932年、日本は現在の中国東北部に「満州国(まんしゅうこく)」という傀儡国家を作りました。広い農地や仕事を求め、多くの日本人が満州にわたりましたが敗戦とともに、苦難の道をたどることになります。人々は侵攻してきたソ連軍に追われ、まさに着の身着のまま、時には徒歩で、日本を目指しました。その混乱の中、多くの子どもが中国人に引き取られる形で中国に残されたのです。彼らは「残留孤児」と呼ばれ、日本政府が認定しているだけでも2818人にのぼります。
「行きなさい」 忘れられない母との別れ
愛媛県で生まれた宇都宮さんは両親に連れられ1943年、満州にわたりました。農業を営んでいた両親の姿、藁ぶき屋根の家…覚えていることはわずかです。終戦後、母や姉とともに貨物列車に乗り、日本へ向かう途中、黒竜江省佳木斯(ジャムス)市の難民収容所に収容されました。しかし母は腸チフスにかかり、寝たきりになってしまいます。そこに現れたのが宇都宮さんの養父母となる中国人夫婦でした。
宇都宮孝良さん
「母親は板のベッドに横たわり、起き上がることができませんでした。私に手を振って『行きなさい』と合図したのを覚えています。とても鮮明に。12歳だった姉も一緒に行きたいといいましたが、養父が『男の子が欲しい。女の子は要らない』と言ったので、一緒に行けませんでした」
それが、家族との別れでした。
宇都宮さんは3歳。覚えているたったひとつの日本語。それは「おかあちゃん」という言葉でした。
農業を営む養父母は決して裕福ではありませんでしたが、宇都宮さんを大事に育ててくれました。収容所で骨と皮だけになっていた宇都宮さんに毎日牛乳を飲ませ、体力をつけてくれました。
宇都宮孝良さん
「養父母は、私を実の息子のように扱ってくれました。おいしいものはいつも私に先に食べさせてくれました。冬には寒くないよう綿の入った服を着せてくれ、本当の親のように気遣ってくれました。だから私は一生、養父母への感謝の気持ちと彼らへの忘れられない思いを抱き続けているのです」