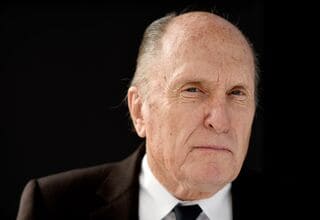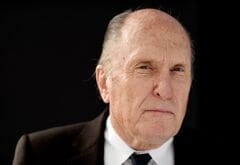(ブルームバーグ):8月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除くコアCPI)は、政府の物価高支援策の影響でエネルギーが下落し、前月から伸びが縮小した。日本銀行の目標の2%は引き続き上回り、年内利上げ観測の支えとなりそうだ。
総務省の19日の発表によると、コアCPIは前年同月比2.7%上昇と市場予想と一致した。3%台割れは9カ月ぶり。日銀目標を上回るのは41カ月連続となる。
政府支援策で電気・都市ガス代の下落幅が前月から拡大し、エネルギー全体では3.3%下落と昨年1月以来の大幅な落ち込みとなった。生鮮食品を除く食料は8.0%上昇と前月の8.3%上昇を下回った。伸び縮小は2024年7月以来。このうちコメ類は69.7%上昇と3カ月連続でプラス幅が縮小した。

生鮮食品とエネルギーを除くコアコアCPIは3.3%上昇と伸びが縮小し、市場予想と一致した。プラス幅の縮小は13カ月ぶり。3%台は5カ月連続となる。総合指数は2.7%上昇と伸びが縮小し、市場予想(2.8%上昇)を下回った。
日銀はトランプ関税の影響などを見極めるため、19日の金融政策決定会合では5会合連続となる政策金利の維持を決める公算が大きい。今回のCPIの結果は物価上昇圧力の根強さを反映している可能性があり、日銀が堅持している利上げ路線を支える内容と言える。
大和総研の久後翔太郎シニアエコノミストは、今回の結果はおおむね想定通り」とし、「国内の物価上昇圧力が引き続き強い状況が確認できた」と指摘。国内の経済・物価情勢に関しては、「着実に利上げを行う環境が整いつつある」と語った。
賃金動向を反映しやすいサービス価格は1.5%上昇と、3カ月連続で同じ伸びとなった。今年の春闘での賃上げ率が2年連続で5%台と高水準になる中、賃金から物価への波及が継続するかが注目されている。
総務省の説明
- 電気・ガス料金負担軽減支援事業の押し下げ寄与はコアCPIでマイナス0.27ポイント。同事業が行われなかった場合のコアCPIは3.0%上昇
- エネルギーのうちガソリン価格の上昇(0.6%上昇)は、直近の原油高を反映
- その他の品目では、外食の牛丼なども前年の値上げの反動で押し下げに寄与。生鮮食品を除く食料は傾向的には上昇している品目が多い
(エコノミストコメントや総務省の説明を追加して更新しました)
--取材協力:藤岡徹.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.