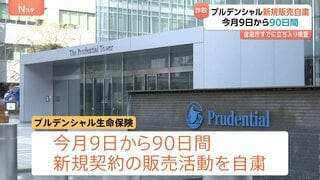見直しにおける留意点
今回の見直しは、“居住用”の“区分所有財産”が対象のため、事業用のテナント物件など構造上主として居住の用途に供することができないもの、一棟所有の賃貸マンションなど区分所有の登記がされていないものは本評価の対象外となります。
また、居住用の区分所有財産でも2階建て以下の低層マンションや、二世帯住宅なども対象外となります。
また、区分所有補正率を求める算式などについては、売買実例価額に基づき統計的に予測した市場価格を考慮して評価額を補正するものであり、将来のマンションの市場の変化を踏まえたものとする必要があることから、適時見直しを行うこととされています。
この見直しについては、3年に一度行われる固定資産税評価の見直し時期に併せて行うことが、合理的であるとして、改めて実際の取引事例についての相続税評価額と売買実例価額との乖離状況等を踏まえ、見直しの要否を国税庁において検討することになります。
なお、居住用の区分所有財産の相続税評価額は、最低でも市場価格理論値の6割程度まで引き上がることにはなりますが、そもそも時価との評価差額が生じない現金や預貯金などと比較すると、時価との乖離は一定程度許容されているともいえます。
また、賃貸の用に供することで、建物は「貸家」、敷地権は「貸家建付地」として評価が引き下がることや、一定の条件を充たすことにより、小規模宅地等の特例の適用を受けることも可能なため、引き続き全体的な相続対策の中で活用を検討していくことも有用かと思います。
ただし、今回の見直しの目的は、課税の公平や納税者の予測可能性等の観点から評価額の乖離を手当てしているものであり、租税回避防止措置として捉えているわけではありません。
つまり財産の取得等が実質的な租税負担の公平を失わせるような租税回避行為と国税庁が判断した場合、これまで通り、評価通達6により、鑑定評価額等での課税処分が下される場合もありますので、行き過ぎた節税対策は裏目に出る可能性がある点については留意しておく必要があるでしょう。
情報提供、記事執筆:MUFG相続研究所 フェロー 玉置 千裕