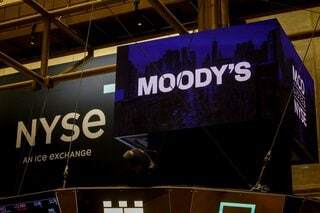(ブルームバーグ):こんにちは。布施太郎です。今月のニュースレターをお届けします。
今、日本の経営者にとって、株価向上は最重要課題となりました。政府や東京証券取引所の改革を追い風に、アクティビスト(物言う株主)の発言力は強まり、機関投資家の議決権行使基準も厳しさを増しています。株価を上げられなければ経営者は解任のリスクに直面し、場合によっては「同意なき買収」の標的とされる時代です。
株主・投資家が待ち望んだ環境の到来と言えるでしょう。しかし、そのことが果たして取引先や従業員、ひいては社会全体にとって有益かどうかは、別の問題です。
「企業は何のために存在するのか」。この根源的な問いは、時代を超えて常に私たちに投げかけられてきました。
夏休みの機会に、少し立ち止まって考えてみたい。そんな思いから、経済学者の岩井克人氏にインタビューをお願いしました。
岩井氏は1947年生まれ。東京大学経済学部卒業後、マサチューセッツ工科大学でPh.D.を取得。イェール大学助教授などを経て、1989年から東京大学経済学部教授を務め、現在は神奈川大学特別招聘(しょうへい)教授、東京大学名誉教授です。2023年に文化勲章を受章しました。主な著書に「二十一世紀の資本主義論」、「貨幣論」、「会社はこれからどうなるのか」、「経済学の宇宙」などがあります。
実は私は、学生時代に岩井氏の初期の著作「ヴェニスの商人の資本論」を読んで以来、その考え方に魅了されてきました。シェイクスピアの戯曲を通して資本主義の本質を解き明かすという手法に感動し、その後も岩井氏の資本主義論、貨幣論、会社論に深い感銘を受けてきた1人です。岩井氏の日本企業に対するメッセージに耳を傾けていただければと思います。
新たな課題
ー日本企業と資本市場の課題についてどのように見ていますか。

「1990年代のバブル崩壊から続いた『失われた30年』が終わりを告げつつある今、新たな課題が浮かび上がっていると考えています。この経済低迷の根底には、中国をはじめとする途上国が低賃金を武器にグローバル市場に参入したことによって引き起こされたデフレがあります。ケインズが指摘している通り、適度なインフレは経済に活力を与えますが、デフレは短期的には不況を引き起こし、長期的には資本形成やイノベーションにとってマイナスです」
「そうした状況の中で2000年代以降、政策当局は資本市場改革や企業統治改革を通じ、株式市場にグローバルなリスクマネーを呼び込むことで経済を再興しようとした。政策意図は理解できます。しかし皮肉にも、リスクマネーの流入よりも、企業が稼いだ資金が株主還元という形で外部に流出する事態を招いてしまった」
ーどういうことでしょうか。
「データを見ると、1998年以降の株式市場での資金調達額は年間2兆円程度で低迷。一方、配当と自社株買いの合計は2000年以降急増し、2023年には配当23兆円、自社株買い16兆円の合計約40兆円に達しています。実に20倍に達しており、企業が生み出した利益が、株主・投資家への還元に大きく傾いている実態が浮かび上がります。しかも、このうち3割は外国人投資家で、年々その比率は上がっています」
「その結果、賃金は上がらず、設備投資も研究開発投資もほとんど増えていない。好転の兆しも見えますが、人的資本投資などへの資金配分は著しく不足しています。株主還元の資金を企業の長期的成長に向けた投資に回す政策が必要です」
「日本の株式市場は、本来の『成長資金を呼び込む場』というよりも、株主が企業の成果を吸い取るための『収奪の場』となってしまっている。これが今、日本の資本市場と企業の抱える根本的な課題だと私は思っています」
2階建て構造
ー日本の経営者は株主に向き合ってこなかったとずっと批判されてきました。
「株式会社という制度の本質的な構造の理解が必要です。私は長年『2階建て構造』と表現してきました。会社とは法人であることによって、モノであるのにヒトとして扱われるという二重性を持っています。株式とはモノとしての会社の別名ですが、2階部分ではそのモノとしての会社を株主が所有しています。それを、機械設備などの具体的な資産とは独立して売買するのが株式市場です。そして、1階部分こそが法人としての会社の実体的な部分で、経営者を頂点とする人的組織が実際の付加価値を創造する場です」
「決定的に重要なのは、株主が具体的な会社資産を所有しているわけではないことです。彼らが所有しているのは、法人としての会社に対する経済的な請求権に過ぎません」
「こういう2階建ての構造を持っているからこそ、会社は多様な目的を持つことができる。2階である株主を重視する会社もあれば、1階、つまり従業員や地域、さらには地球環境などを重視する会社もある。本来の会社の構造を理解すればもっと多様なガバナンスの在り方、経営の方向性が見えてくるはずです」
ー上場会社の非上場化が増えています。例えばMBO(経営陣が参加する買収)です。
「それは企業が株式市場と決別する動きにほかなりません。アクティビストはもちろん、機関投資家までもが株主の利益ばかり主張し、研究開発や設備投資、人材育成といった将来への投資を軽視する発想。この短期的利益偏重が、リスクマネーを通じた企業の長期的育成という株式市場の本来的な機能をむしばんでいるのです」
「その背景には『会社は株主のものである』という株主主権論があります。代表的なのが経済学者のミルトン・フリードマンによる『会社は株主が利益を得るための手段に過ぎない』という考えです。しかし、これは株式会社が法人であることを無視し、株主が直接会社資産を所有しているかのような誤謬(ごびゅう)に立脚しています。この理論的欠陥こそが、資本市場の機能不全を招いた根幹なのです」
バークシャーとグーグル
ー米国では株主主権論に基づく企業が主流ですね。
「そうとは言い切れません。例えば、世界の時価総額ランキングでトップ10に入る投資会社のバークシャー・ハサウェイ。毎年ネブラスカ州オマハで開かれる株主総会は『資本主義のウッドストック』とも呼ばれ、会長兼CEO(最高経営責任者)のウォーレン・バフェット氏の言葉を聞くために5万人近くの株主が集まります。まさに株主資本主義の象徴のように見える」
「でも、実態は全く違う。バークシャーはA株とB株という二種類の株式を発行しています。ところが、一般株主が買うB株の議決権はごくわずかで、バフェット氏や彼の周辺が保有するA株に圧倒的な議決権がある。つまり、株主の意見に耳を貸すふりはしても、実際には物言う株主に経営を乱されることはないようにつくられています」
「もう一つは、バフェット氏は基本的に長期投資家で『理想的な投資期間は無限だ』と言ってはばからない。またバークシャーの本社は、アップルやコカ・コーラや日本の商社に投資する一方で、100%子会社として保険や鉄道、エネルギー会社なども持っている巨大コングロマリットでもあります。だが、子会社の経営にはほとんど口を出さない。彼の相棒だったチャーリー・マンガー氏は『譲位(アブディケーション)に近い、ほとんど完全な分権化(デリゲーション)だ』と言っています」
「グーグル(現アルファベット)も同様です。バークシャーを見習って種類株制度を導入していますが、A株の10倍の議決権があるB株は創業者たちが握っています。C株には議決権はありません。つまり、資本市場にはアクセスしつつ、経営の主導権は譲らない」
「このように、一見すると株主主権的に見える企業が、実は物言う株主を抑え込み、敵対的な買収は絶対にできない仕組みを持っているのです。逆説的なのは、かえってそのことで長期的な視野を持った経営ができ、従業員や研究者もイノベーティブな技術や商品の開発に専念でき、結果的に資本主義的な成功をもたらしていることです」
会社の目的
ーでも、日本の経営者は株主や市場の要求に背を向けることはなかなかできません。
「ソニーグループの復活劇を挙げてみましょう。2013年にソニーは、米アクティビストのサードポイントからエンターテインメント事業を売れという要求を受けました。これに対して、当時の平井一夫社長が明確に『ノー』と言ったのです」
「なぜそれができたのか。ソニーという会社が『目的』を持っていたからです。それにはもちろん株主の利益を上げることも含まれているかもしれないが、それだけじゃない。例えば『感動を与える』とか、ちょっと格好をつけた言い回しですが、社会的な目的を掲げて経営していた。つまり、企業としての『パーパス』があった」
「そして、そのパーパスに照らしてエンターテインメント部門を切り離すことは会社の本来的な存在意義を毀損(きそん)すると主張した。もちろん、平井さん自身がその事業部門の出身だったというのもあるかもしれないけど、やはり企業としての目的意識が非常に強かったからだと思います。株主にきちんと向き合いながらも『自分たちは株価の最大化だけが目的ではない』と言い切れたこと、それがアクティビストを退け、ソニーを守った」
「日本の多くの会社の経営者に欠けているのは、自分の会社が何のために存在しているのか、何を目的にしているのか、それをはっきり言えないということではないでしょうか」
ー株主は大切ではないのでしょうか。
「もちろん、株主はリスクマネーを提供してくれる存在ですから、それに対して報酬、見返りを与えるのは当然です。でも、それと同時に会社というのは、それ以外の目的をきちんと持っているべきで、そうでないと組織として成り立たない」
「最近は『パーパス経営』がはやっていて、多くの会社がそれらしい文言を掲げています。パーパスという言葉を使うかどうかは別にしても、会社が『何のために存在するのか』という長期的な目的を持つことは根源的です。それがなければ、短期的な株主の要求に正面から向き合えず、場当たり的対応に陥ってしまう」
「日本は米国的な、つまりフリードマン的な理論に引っ張られてしまっている。これに対して欧州は、必ずしも成功しているわけではありませんが、したたかに株主主権論に抵抗しています。フランスなどはパーパスを定款に明記するようにしています。株主主権を強調し過ぎると、かえって株式市場そのものが機能不全に陥るリスクが生じるのです。これに対抗するという意味でも、パーパスには意義があります」
イノベーションの力
ーサステナビリティー経営の観点から非財務情報の開示義務化などで、株価至上主義にとどまらない経営が可能になるという見方もあります。
「社会全体が持続可能性を目指すのは正しいと思います。ただ、同時に資本主義の中で企業経営を行う以上、経営者がリスクを取る判断力や決断力が極めて重要です。ですから、非財務情報の開示などさまざまなことを義務化し過ぎると、本来の資本主義に重要な、経済学者のシュンペーターが言うようなイノベーションの力が失われてしまうリスクがある」
「本来、経営者とは、研究開発や設備投資、人材投資など、将来の成長のための投資をきちんと行う人です。経営者が自ら信じる戦略を持ち、それを実行する胆力が必要です。そして失敗したら潔く身を引く。そういう覚悟を持つのが経営者ではないでしょうか」
「例えば、バフェット氏はフリードマンを直接は批判してはいませんが、彼の発言から見て明らかに軽蔑している。独自の哲学を持って投資し、子会社経営も自主性を重んじている。そして、成功している。グーグルも創業者らが経営していた頃は、主流のコーポレートガバナンスの枠組みにはとらわれていなかった。それで成功した」
「企業という言葉の英語は『エンタープライズ』ですが、その言葉の中にイノベーションという意味が込められています。ところが、今の日本企業はガバナンス・コードなどで締め付けられ、逆にイノベーションへのエネルギーを失っている気がしてなりません」
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.