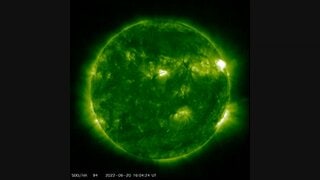(ブルームバーグ):米財務省は四半期定例入札に関する発表を30日に行う。足元では、短期証券(Tビル)発行に偏重する財務省の姿勢がどこまで持続可能かという点が議論の焦点になっており、どのような手掛かりが示されるか注目される。
ベッセント財務長官は、イエレン前長官が中・長期債の発行を人為的に抑制し、選挙前に借り入れコストを低く抑えていると批判していた。そのため就任当初は中・長期債の発行をどれほど迅速に増やすかに関心が集まっていたが、ベッセント氏は長期債利回りが高水準にあることを理由に、中・長期債の発行を増やす意向がないことを繰り返し明言している。
JPモルガン・チェースの米インフレ戦略責任者、フィービー・ホワイト氏は電話インタビューで、「最近の発言を聞く限りでは、今すぐ中・長期債の発行を増やす必要はないとの認識があるようだ。直近の資金需要はTビルの発行増で対応可能とみている」と指摘した。
現時点では、マネー・マーケット・ファンド(MMF)の拡大などを背景に、「Tビルへの需要が非常に強い状況」が続いているという。一方で、財務省がTビルに依存しすぎると、借り換えのたびに利払いの変動性が高まるといったリスクもある。
来週実施される四半期定例入札については、過去数四半期から変更はなく、3年、10年、30年債の計1250億ドル(約18兆5200億円)相当の発行が見込まれている。具体的な内訳は以下の通り。
- 8月5日:3年債580億ドル
- 8月6日:10年債420億ドル
- 8月7日:30年債250億ドル
ディーラー各社は、30日に公表される声明で、昨年1月以来維持されている「少なくとも今後数四半期は」中・長期債の発行規模を据え置くとのガイダンスに変更があるかに注目している。
仮に2026年2月以降の中・長期債発行拡大を当局が念頭に置いている場合、「少なくとも」の文言を削除するかもしれないと、ホワイト氏らJPモルガンのアナリストらは最近のリポートで述べた。
一方、バンク・オブ・アメリカ(BofA)は今月、2026年2月に中・長期債の発行拡大が始まるとの従来予想を撤回し、2027年以降への先送りを予測。シティグループは2026年5月を見込んでいるが、さらに遅れるリスクもあるとしている。
今回の発表では、ベッセント氏が債務総額に対するTビル発行残高の比率上昇をどこまで許容するかについて指針が示される可能性がある。
シティグループのストラテジスト、アレハンドラ・バスケス・プラタ氏とジェイソン・ウィリアムズ氏によると、財務省が中・長期債の発行拡大を控えた場合、Tビルの割合は2028 年までに27%に上昇する見通しだ。そうなれば新型コロナ禍の救済措置のために発行が急増した2020年のピークを上回り、2033年までには41%に達する可能性があるという。ただ、両氏はその水準に達するとは予想しておらず、財務省は約25%を「ソフト上限」とする可能性が高いとみている。
原題:For Bond Dealers, It’s Now All About Bills at Bessent’s Treasury(抜粋)
(最終2段落を追加して更新します。更新前の記事では第3段落目の社名をJPモルガン・チェースに訂正済みです)
--取材協力:Alex Newman、Alex Harris.
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.