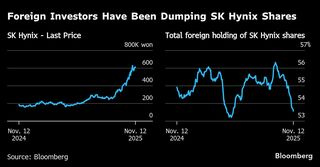(ブルームバーグ):日米関税交渉が合意に至り、一定のめどがついたことについて、財界からは評価の声が上がった。一方で米国が自国優先主義に傾く中、今回の合意は通過点であり、今後の対応が肝要だとの見方もある。
経済同友会の新浪剛史代表幹事は、「自動車を含む関税の全面的な引き上げが回避されたことは、企業の現場にとって重要な防波堤となり得る」と評価した。日本貿易会の安永達夫会長は23日午前の定例会見で、関税交渉で日米が合意したとの報道を受け、不透明感が拭われたことを評価したいとした一方で、日米合意は一つのマイルストーンに過ぎず、今後が重要になるとコメントした。

新浪氏は「米国の自国優先主義への傾倒、国際協調への関与低下」の流れは変わる訳ではなく、この変化を前提として日米関係の強化や日本の主導による国際協調の枠組みの再構築、日本経済のレジリエンス強化を図ることが急務だとした。
一方で、一部では不安の声も上がる。日本商工会議所の小林健会頭は、「15%の関税が課されることは遺憾と言わざるを得ない」との声明を発表。多くの中小企業の経営に影響が及ぶことへの懸念を示した。読売新聞によると、経団連の筒井義信会長は報道陣の取材に今回の合意を高く評価しているとしながら、税率15%はGDP(国内総生産)成長率への影響がそれなりに大きいのも事実だと懸念を表明した。
企業は悲喜こもごも
米国は日本にとって最大の輸出相手国で、うち自動車や自動車部品は全体の金額の約3分の1を占める。関税率が従来示されていた25%から15%になったことで、日本企業にかかる負担は低減されたものの、今後もトランプ米大統領の「ディール」に企業が振り回される懸念は拭い切れない。
輸出企業からは悲喜こもごもの声が聞かれた。東芝は日本から米国に電池や火力発電機、半導体製造装置などを輸出しており、広報担当者は関税率が15%で決着したことで当初想定していた事業への影響が軽減されると述べた。今後の対応については、価格転嫁や仕向け地の変更などを基本方針として検討するという。
事業環境の改善を期待する向きもある。日本工作機械工業会の坂元繁友会長(芝浦機械社長)は同日の記者会見で、不透明感が解消されたことで、自動車関連などこれまで先送りしていた設備投資案件が具体化し、工作機械メーカーの受注環境が良くなる可能性への期待を述べた。
一方、村田製作所は市場の冷え込みや部品需要の減少など間接影響を懸念する。例えば今期(2026年3月期)のスマートフォン市場を11億7000万台と見込んでいるが、当初想定より1%下がると約50億円の減収になると試算しており、今後も影響を調査・分析するとしている。
(情報を追加して更新します)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.