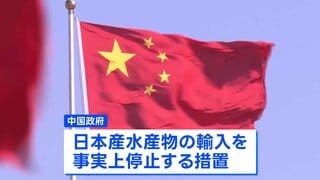(ブルームバーグ):日本銀行が金融危機などの際に金融機関から買い入れた株式の売却が終了した。時価で70兆円程度に達する上場投資信託(ETF)の処分の議論につながるかが焦点だが、環境が整うかは米関税政策の影響次第の面もある。
日銀が14日に公表した7月10日現在の営業毎旬報告では、金銭の信託(信託財産株式)の記載がなくなった。金融システムの安定確保を目的に日銀が2002-04年と09年に金融機関から購入した株式の残高を計上していたもので、前回公表分の6月30日現在の残高は約25億円だった。

日銀は同株式の売却を16年4月に開始し、26年3月まで10年かけて処分するとしていた。毎月、簿価で100億円前後の売却を進めてきた結果、売却前に同1兆3500億円程度あった保有残高は、予定よりも早くゼロとなった。
中央銀行にとって異例の措置として買い入れた株式の処分が完了したことは、象徴的な出来事と言える。日銀が金融政策の正常化を進める中で、大規模な金融緩和策の一環として大量に買い入れたETFの処分が大きな課題として残っているためだ。
フィリップ証券の笹木和弘リサーチ部長は、株式売却の終了は「一つのステップになり得るが、基本的に日銀がETFの売却に行くのはまだ早いだろう」とみている。市場に影響のない形でETFを処分することが重要だとした上で、「順番としては金利の引き上げがある程度、形がついた後だと思う」と語った。
保有ETFの処分
白川方明元総裁の下で10年12月に始まったETF買い入れは、後任の黒田東彦前総裁によって増額が繰り返された。植田和男総裁が昨年3月、17年ぶりの利上げと同時にETFの新規購入も終了したが、保有残高は今年3月末時点で簿価37兆円、時価70兆円に膨らんでいる。
日銀はETFの処分に際し、日銀の損失を回避することや、市場にかく乱的な影響を与えないことをなどを基本要領に定めており、市場環境は売却検討の要素となる。日経平均株価は6月末に一時4万円台を回復したものの、その後は日米関税交渉の混迷を背景に再び軟調になるなど神経質な地合いが続いている。
植田総裁は5月の国会答弁で、ETF処分について「時間をかけて検討している状態が続いている」と従来の説明を繰り返した。日銀は昨年7月に国債買い入れの減額計画を決め、バランスシートの正常化に着手した。6月に決めた新計画では市場安定に配慮して減額幅を縮小しており、ETF処分も慎重に検討する可能性が大きい。
(市場関係者のコメントを追加して更新しました)
--取材協力:アリス・フレンチ.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.