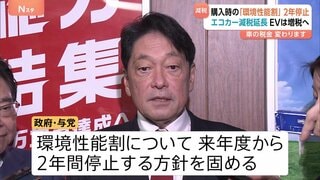勝者すら不幸にする壮大な“ゲーム”の正体
著書のタイトルを『トレーディング・ゲーム』とした理由について、スティーヴンソン氏は、現代社会のあらゆる側面が「ゲーム化」されているからだと説明します。
教育も、就職も、そして彼が身を置いた金融市場も、すべてがゲームでした。しかし、物事をゲーム化すると、そこから人間性が失われると彼は指摘します。
街角のホームレスを「ゲームの敗者」と見なしてしまう冷酷な視点は、このゲーム思考の弊害です。この思考が社会の深刻な不平等を正当化し、人々を不幸にしているのです。
この本の重要なメッセージは、ゲームの勝者すら幸せにはなれない、という点にあります。スティーヴンソン氏自身、大金を稼ぎながらも、精神的には決して幸福ではありませんでした。

彼の周りにいた裕福な同僚たちの多くも同様であり、一日中働き詰めで貧しかった父親の方が、よほど幸せそうに見えたといいます。このシステムは、敗者だけでなく勝者からも幸福を奪う、機能不全に陥った仕組みなのです。
彼が会社を辞めようとした際、上司たちとの間で繰り広げられた壮絶な心理戦も、まさに「ゲーム」そのものでした。
「良い警官と悪い警官」作戦のように、ある会議では怒鳴られ、次の会議では優しくされる。彼らの言葉は本心ではなく、望む結果を得るための戦略的な駒に過ぎませんでした。
誠実さが失われ、すべてが駆け引きとなる。その非人間的なコミュニケーションは、現代社会の権力構造の縮図であると、スティーヴンソン氏は分析します。
日本への警鐘、そして若者は団結せよ
「第二の故郷」と語るほど日本を愛するスティーヴンソン氏は、だからこそ、日本の未来を憂いています。
現在の日本には、まだイギリスやアメリカほどの絶望的な格差社会には至っておらず、健全な「中流階級」が存在します。しかし、格差は確実に拡大しており、このままでは社会が二極化する道をたどる危険性があると警告します。
では、どうすればいいのか。スティーヴンソン氏は、個人の努力を否定しません。若者は全力を尽くすべきだと語ります。
しかし、同時に、この社会が「親ガチャ」に象徴されるような、きわめて不利なゲームであることを認識すべきだと強調します。
そして彼が最も重要だと訴えるのが、「個人」で戦わないことです。

かつての英国首相サッチャーの「社会など存在しない」という言葉が象徴する個人主義が、富める者と持たざる者の分断を加速させました。
持たざる者が持つ唯一の戦略的な強みは「数の力」であり、人々が連帯し、協力して集団の利益を守る以外に道はない、と彼は説きます。
そのためには、政治への関心が不可欠です。多くの若者が政治に無関心だったイギリスでは、その間に不公平なルールがまかり通り、若者たちは今、多くを失いつつあります。
普通の人々が経済の仕組みを学び、協力し、自分たちの利益を守るために声を上げる。
それこそが、自分たちの生活を守り、より良い社会を築く唯一の方法であると、ギャリー・スティーヴンソン氏は力強く訴えかけているのです。
※この記事はTBS CROSS DIG with Bloombergで配信した「1on1」の内容を抜粋したものです。