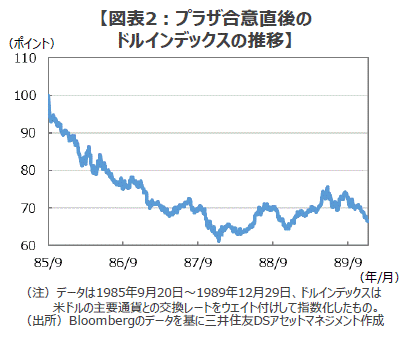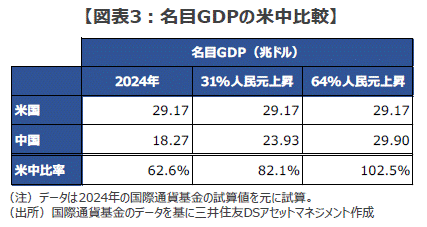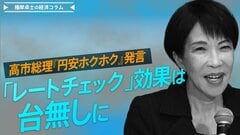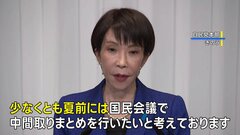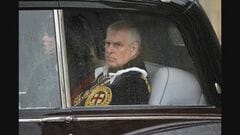それでも「ドル高が米国の国益」なワケ
こうした経緯を見ていくと、米国が「報復」として円高カードを切ってくることに市場が戦々恐々とするのも、ある意味仕方がないように思えてきます。とはいえ、こうした懸念は杞憂に終わる可能性が高いのではないでしょうか。
というのも、4月のトランプ関税ショックで米国株が急落した際に、米国債と米ドルが揃って売られる「トリプル安」が起こったことで、ベッセント財務長官以外のホワイトハウスの高官たちも、「市場の恐ろしさ」が身に染みているはずだからです。
覇権国の屋台骨を支える「ドル高」
①米国民が優雅な消費生活を満喫し、②米国企業が巨額の投資資金を世界中からかき集め、そして、③米国が世界最強の軍備を維持するには、海外からの投資や借入が必要不可欠といって良いでしょう。そして、こうした覇権国としての地位を維持するためには、「ドル高」をテコにした円滑なファイナンスが必要不可欠といって良いでしょう。
対中戦略を大転換させた米中逆転への危機感
米国の国家戦略においてドル高が極めて重要なのは、経済規模で世界一を維持することが米国の覇権に挑む中国に対抗する上で決定的に重要だと思われるからです。
米政府は2017年に取りまとめた『国家安全保障戦略(NSS2017)』の中で、中国を「米国の安全や繁栄を侵食しようとする挑戦国(Attempting to erode American security and prosperity)」として再定義し、その強硬姿勢を鮮明にしました。
この米国の対中政策の大転換の背景には、中国が見せる領土的な野心に加えて、米中の経済規模が逆転することへの危機感があったように思われます。
当時、経済成長著しい中国は購買力平価基準で見たGDPで2017年に米国を抜き去り、当時は名目GDPでも遠からず米中逆転が起きるとする予測が大勢となっていました。
世界の主要国の防衛予算は名目GDPに対する比率が一つの目安になりますが、名目GDPで米中が逆転すると、軍事力でも米中逆転に繋がる可能性が高まります。
このため、もし名目GDPの米中逆転が実現すると、人口、経済規模、軍事力、経済成長力などの各点で米中逆転が生ずることとなり、米国は覇権国の地位から引きずり降ろされる可能性が高まります。
プラザ合意2.0が「良くできたナラティブ」なワケ
こうした点を押さえていれば、最近、市場関係者の間で度々取りざたされる「マールアラーゴ合意」や「プラザ合意2.0」といった、大幅なドル高是正のための国際協調は、「よくできたナラティブ(Narrative、物語、フィクションのこと)」に過ぎないことが分かってきます。
なぜなら、1985年9月に結ばれたプラザ合意(1.0?)では、国際協調によるドル安誘導の結果、主要通貨に対する米ドルの価値を指数化したドルインデックスで見た貿易相手国の通貨価値は、1年後の1986年9月には約31%、そして、約2年3カ月後の1987年末には約64%上昇しました。
人民元急騰で生じる名目GDPの米中逆転
現在、中国の名目GDPは約18.27兆ドルで、約29.17兆ドルに達する米国の約63%に留まります(2024年の推計値)。
しかし、プラザ合意と同様なインパクトのドル安が対人民元で発生すると、1年後に中国のGDPは米国の約82%に、そして2年3カ月後には米国の約103%に達し、米中の名目GDPは逆転することとなります。
こうした事態は、国益を重視するトランプ政権や、ドル高の維持が米国の覇権を維持する上で不可欠であることを知るベッセント財務長官が、許容する可能性は極めて低いように思われます。
そう考えると、米国がちらつかせる「為替カード」は、例えば採算の怪しい巨額の投資案件への出資や、安全保障の分野で日本に無理筋の譲歩を迫るための「交渉カード」に過ぎないのではないでしょうか。
米中の通商摩擦が緊張緩和へと大きく動いたことで、株式市場では楽観ムードが広がりつつあります。一方、為替市場に目を転じると、アジア通貨が乱高下するなど、神経質な展開が続いています。
こうした株式市場と為替市場のコントラストの背景には、米国の対中包囲網に非協力的な同盟国に対する「報復への懸念」があるのかもしれません。
というのも、米国はディールを通じた対中包囲網の構築に手間取る中で米国市場のトリプル安に見舞われることで、対中関税交渉で大幅な譲歩に追い込まれた可能性が指摘されているからです。
ただし、「プラザ合意2.0」のような国際協調による大幅なドル安誘導が実施される可能性は極めて限定的でしょう。というのも、かつてのプラザ合意のようなドル安政策が実行されると、名目GDPの米中逆転に繋がりかねず、米国の覇権を危うくする可能性が高いからです。
このため、仮に米国が「ドル安」をちらつかせたとしても、無理筋の要求を通すための交渉カードにすぎない可能性が高そうです。
(※情報提供、記事執筆:三井住友DSアセットマネジメント チーフグローバルストラテジスト 白木 久史)