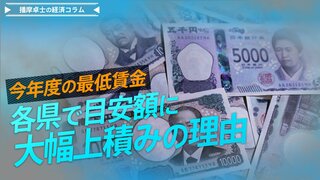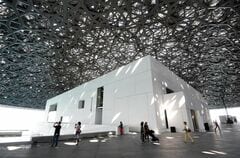(ブルームバーグ):13日の日本市場では株式が続伸し、東証株価指数(TOPIX)は2009年以来の13日連続高となった。米国と中国の貿易合意を受けて投資家のリスク選好姿勢が強まった。安全資産への需要が低下し債券は中長期債が下落(金利は上昇)。円は前日に売られた反動で1ドル=147円台に上昇した。
日経平均株価は3万8000円台を回復し、2月27日以来の高値で終えた。米中は週末の貿易協議で相互の関税率を一定期間引き下げることで合意。トランプ大統領は12日、今週中に習近平国家主席と話す可能性が高いとの認識を示した。
野村総合研究所の木内登英エグゼクティブ・エコノミストはコラムで、米国による対中関税率が145%から30%に引き下げられることは、日本経済にとって朗報だと指摘。日本の国内総生産(GDP)への押し下げ影響は0.45%と、これまでの1.01%と比べて大幅に緩和するとの試算を示した。
株式
東京株式相場は続伸。米中関税交渉が進展し、景気や企業業績の先行き不透明感が後退した。自動車や電機、機械など輸出関連のほか、医薬品や銀行株が買われた。
T&Dアセットマネジメントの酒井祐輔シニア・トレーダーは、関税懸念が和らぎ、株式相場は厳しい状況から回復していると指摘。株高の背景に外国人投資家による日本への資金シフトがあるとし、国内投資家も買い始めているとの見方を示した。
一方、為替の円安一服もあり、買い一巡後の相場の上値は重かった。ロベコ香港のポートフォリオマネジャー、ケルビン・リョン氏は、米中合意により日米間でも合意に至る可能性が高まったとした上で、日本で楽観ムードが急速に広がっていることは懸念材料だと指摘。株価指数の水準を見る限り、期待が先行していると話した。
債券
債券相場は中長期債が下落。米中が関税率の大幅な引き下げで合意したことを受け、リスク選好の高まりから安全資産としての需要が低下した。この日行われた30年債入札は無難な結果だったとの声が出ており、30年債中心に超長期債は上昇した。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の藤原和也債券ストラテジストは入札結果について、応札倍率はやや弱めだったが、最低落札価格が予想と一致し、無難な結果だったと語る。懸念されたイベントを消化したことで「いったんは超長期債の買い材料になるものの、根本的な需給懸念は解消されていない」として、先行きには慎重な見方を変えていない。
太陽生命保険の佐藤義剛運用企画部長は「30年債はターゲットにしておらず、この水準で買うことは今のところ考えていない」と話す。超長期債は入札が続き需給が弱含む可能性がある上、「ここ数日は説明の付かない金利上昇が続いており、今後も値動きが定まらない展開が続く可能性が高い」と指摘。買い急ぐことはせず、淡々と平準的に買っていくと述べた。
新発国債利回り(午後3時時点)
為替
円相場は1ドル=147円台後半に上昇した。米中摩擦の緩和期待で前日にドル買い・円売りが進んだ反動が出た。加藤勝信財務相が来週、ベッセント米財務長官と為替について協議することを検討していると発言したことも円買いにつながった。
ソニーフィナンシャルグループの森本淳太郎シニアアナリストは、米中の関税は「予想以上に下がった印象だが、90日の期限付きで不透明感も残るため、過度に楽観的にはなれない部分もある」と述べた。
あおぞら銀行の諸我晃チーフマーケットストラテジストは、前日の反動に加えて加藤財務相の発言もあり、ドル・円は上を攻めづらくなっていると述べた。関税政策が緩和的になり、「日本銀行が利上げに動きやすくなったこともドル・円の上値を抑えている」との見方を示した。スワップ市場で日銀の年内利上げ確率は8割程度と、9日時点の5割から回復している。
この記事は一部にブルームバーグ・オートメーションを利用しています。
--取材協力:長谷川敏郎、我妻綾、佐野日出之.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.