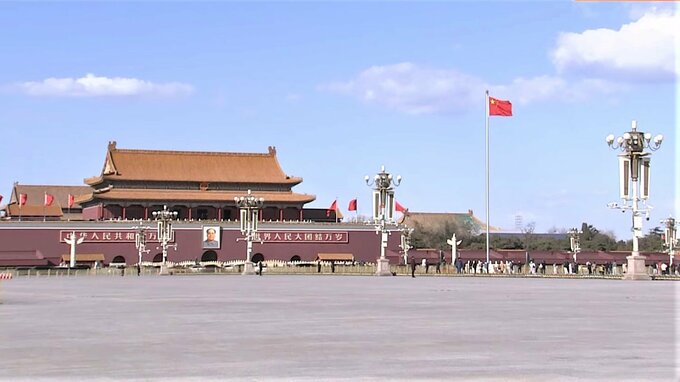中国では、人口高齢化が想定を上回るスピードで進んでいる。公的年金保険の一つである都市職工基本年金保険基金は2035年より前に残高がマイナスに転じる見通しで、国家財政を揺るがす問題となる。
急ピッチで進む高齢化
国家衛生健康委員会は、2022年8月、党機関誌『求是』に「新時代の人口に関する新たな一章を記す」という論文を掲載し、第14次五カ年計画中(2021~25年)に人口減少に転じるという見通しを示した。そのうえで、高齢化の進展により、2035年に60歳以上の人口が全体の3割超に達する一方、核家族化により家庭の介護および育児の機能が弱まるとした。
中国の人口高齢化の特徴の一つは、なんといってもそのスピードが速い点にある。国連の「世界人口見通し2022年版」の中位推計から、人口全体に占める60歳以上の割合がどのように推移するかをみると、日本は1966年に10%に達し、20%を超えるのに28年、そこから30%を超えるのに15年かかった。そして、40%を超えるのに25年かかると見込まれる。中国は、2000年に10%に達し、20%を超えるのに24年と、日本とそれほど変わらないが、30%を超えるまでの期間は11年、そして、40%を超えるまでの期間は17年と予想されており、いずれも日本よりかなり短い。この背景に一人っ子政策があるのは言うまでもない。
上昇続く高齢者扶養率
人口に占める60歳以上の割合は上昇するものの、60歳以上の高齢人口そのものは2055年頃にピークを迎え、その後減少に転じる。これは、年金財政の持続性という点からは朗報であるようにみえるが、高齢者を支える現役世代の人口がそれ以上に減少するため、年金財政がその後もひっ迫の度合いを増すのは確実である。15~59歳の生産年齢人口に対する60歳以上の人口の比率である高齢者扶養率は2080年頃まで上昇を続ける見通しである。
年金財政の悪化が懸念されるのは、「職工」と呼ばれる国有企業や大規模民営企業の就業者を対象とする都市職工基本年金保険である。公的年金保険の一つである同保険は賦課方式と個人積立方式を合わせた設計で運営されているため、高齢者扶養率が上昇すると年金財政は必然的にひっ迫する。労働力の流出と出生率の低下により高齢者扶養率が急速に上昇した黒竜江省では、2013年から同基金の支出が収入を上回るようになり、2016年には積立金も底を突き、基金残高がマイナスとなった。足りない資金は省財政で補てんされているとみられるが、高齢者扶養率のさらなる上昇を考慮すれば、同省の都市職工基本年金保険は制度として維持不可能といえる。