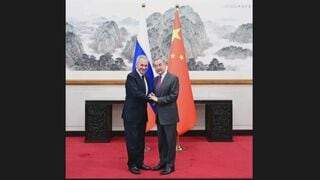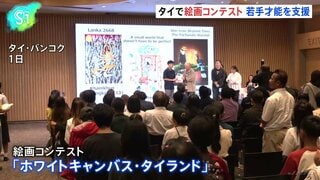中国にとっての課題と日本にとっての課題
1|中国にとっての課題 : 生成AIのポテンシャルを最大化し、脅威を最小化できるか
今回のDeepSeekショックは、産業高度化や国際社会でのプレゼンス強化を目指す中国にとって朗報ではあるが、手放しで喜ぶことはできないだろう。今後は、生成AIの急速な発展に対して、中国政府がどのように臨むかが焦点となる。
例えば、生成AIに関する法制度の整備だ。中国は、2022年から既に段階的に関連する制度を導入してきたが、包括的な法制度はまだ存在しておらず、24年から「人工知能法」の制定に関する議論がスタートしたばかりだ。現状、フェイクニュース対策や依存予防のほか、上述の敏感なトピックに対する管理など、想定される悪影響を防ぐための規制的要素もみられるものの、全体的なスタンスとしては規制よりも推進に重きを置いたAI政策となっているようだ。今後、生成AI普及による影響や、AI政策のスタンス、具体的な法制度の整備がどのような展開をみせるか、注視が必要だ。
また、雇用や所得格差に対する悪影響を緩和、予防するための対応も必要となる。重要なのは、農村戸籍を持つ人々への対応だ。中国では、出生地が都市か農村かによって戸籍の種類が分かれており、これが公共サービスや社会保障などの水準にも影響している。とくに農民工と呼ばれる都市で働く農村戸籍の労働者は、都市戸籍の労働者に比べて、教育などの面で十分な公共サービスを享受できていないことが問題となっている。制度的要因により教育機会に格差が生じた結果、AIの発展にキャッチアップできずに発展から取り残されることがないようにすることが求められる。戸籍制度改革はこれまでも着実に進められてきてはいるものの、AIの普及スピードに後れをとらないよう進めていけるかが課題となる。
このほか、経済政策の観点では、生成AI開発で再びその実力を見せつけた民営企業をどのように社会に位置づけるのか、中国政府は再考を迫られている。最近では、習近平総書記自らが、有力な民営企業家を招いて座談会を開催し、民営企業の発展を支援する姿勢を強調するなど、民営企業重視の動きが強まっているが、かつては同様に発展を支援した後、民営経済が党の統治を脅かすほどの影響力を有するようになったことで、規制強化の方向に舵を切った。今後、党の統治と民営経済の発展がどのようなバランスで両立を実現するか、中国政府の試行錯誤や民営企業の模索が続くだろう。
2|日本にとっての課題 : 中国発生成AIと無関係ではいられず
日本としては、急速に台頭する中国発の生成AIとどのように向き合えばよいだろうか。
中国発生成AIに関していえば、DeepSeekなど中国企業が提供するサービスについては、中国への情報漏洩などの懸念から、利用に対して慎重となることは止むを得ないだろう。他方、公開されたソースコードや、米国企業のクラウド上で提供されたサービスを利用することで、そうしたリスクを回避しつつ、中国発生成AIを活用して生産性の向上を図る、あるいは日本での生成AI開発に役立てることはできる。生成AIを巡るグローバルガバナンスに関しては、国・地域によりスタンスが分かれるなか、中国のスタンスは日本に近いとの見方もある。25年2月に開催された「人工知能アクションサミット」に代表されるように、日本も引き続き中国とともに国際的な枠組みの形成に積極的に参加していくことが求められる。経済、外交の両面で、中国発の生成AIと無関係ではいられないということだ。
だが、より重要なことは、中国がDXやGXといった世界の潮流を踏まえ、今後もハイテク分野で米国と同等、あるいはそれを超える成果をあげ、EVや生成AIに次ぐ様々な「中国発」が世界を席巻する可能性が高まっていることだ。かつての賃金上昇に始まり、不動産不況による経済の低迷や米中対立に伴う地政学リスクの高まりなど、弱さが目立つ中国経済だが、今回のDeepSeekショックは、ハイテクという強さも急速に備えつつあることを改めて世界に知らしめた。弱さと強さが併存する歪な構造の中国と、今後加速が見込まれるハイテク分野における世界のデカップリングに対してどう臨むか、日本企業は戦略をより深めていく必要に迫られているといえよう。
(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 経済研究部 主任研究員 三浦 祐介)