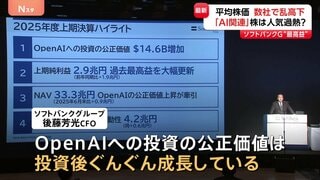(ブルームバーグ):日産自動車は13日、今期(2025年3月期)の営業利益見通しを1200億円と、従来見通しの1500億円から下方修正した。ホンダと進めていた共同持ち株会社計画が破談になったことで日産の協業先探しは振り出しに戻ることになり、一部工場の閉鎖など従来のリストラ計画を強化して当面は単独での経営再建に注力する。
日産の決算資料によると、今期の営業利益は為替や原材料価格が若干のプラス要因となるものの、販売台数減やインセンティブ(販売奨励金)が重しとなって従来見通しを下回る見通し。今期は800億円の純損失と、昨年7月に公表していた3000億円の黒字から一転赤字となる。昨年11月時点で合理的な算定が困難として非開示としていた。
日産は経営悪化が顕著になった昨年11月に生産能力2割や人員9000人の削減を柱とするリストラ策を公表。当初は生産シフトの調整で対応し、工場閉鎖は伴わない方向で検討していたが、同日に発表された進捗(しんちょく)ではタイ第1工場含めて世界で3工場を来期(26年3月期)から27年3月期にかけて閉鎖する方針を示すなど強化させた。
これらに伴い、計6500人を削減。26年度に中国を除く損益分岐台数を310万台から250万台レベルに引き下げ、営業利益率4%を安定的に確保できる体制の構築を目指す。さらに早期退職プログラムの導入を含めて一般管理部門で2500人を削減。執行役員制度の廃止に伴い、新たに執行職制度を導入し、人数は2割削減して階層をスリム化するという。
内田誠社長は決算会見で自身の進退について問われると「業績の低迷に歯止めをかけ、現在の混乱を収束させることが喫緊の役割」とした上で、「果たすべき務めに一日も早くめどをつけ、可及的速やかに後任にバトンタッチしたい」と述べた。
TOB検討せず
一方、ホンダと日産は13日、共同持ち株会社設立に向けた協議や検討を打ち切ることで合意したと発表した。
両社の発表資料によると、自動車の電動化に向けて変化の激しさが増す市場環境において、意思決定や経営のスピードを優先するには計画の実行を見送ることが適切との判断にいたったとしている。三菱自動車を含めた3社間での覚書についても解約することを合意したと発表した。24年8月に取り決めた、三菱自も含めたソフトウエアなどの分野での協業については継続するとしている。
ホンダの三部敏宏社長は会見で、「厳しい判断」を迫られた際に当初の方式では判断に時間がかかる可能性があると判断し、合意が撤回されることも覚悟で日産側に株式交換による経営統合を提案したと明らかにした。計画が実現しなかったことを「大変、残念に感じている」とした上で、日産に対する敵対的TOB(株式公開買い付け)については考えたこともないしその予定はない、と述べた。
結果的にこの枠組みで合意点を見いだせなかったといい、一部で報道された日産のリストラ計画にホンダが納得できなかったということはないと述べた。株式交換比率についても具体的な数値は提示しておらず、その部分で折り合わなかった事実もないとした。また、交渉において国の関与は一切なかったと述べた。
日産の内田社長も会見で、今の状況では一社では難しく、ホンダの提案を真摯(しんし)に議論したが同意にいたらず残念だとした。
日産の筆頭株主である仏ルノーは日産取締役会の決定を受けて声明を公表。ホンダと日産の計画での条件ではプレミアムが含まれておらず、受け入れ難かったとした。ルノーとしては再建計画の実行に注力する日産の意向を歓迎し、同社との間のプロジェクトへのサポートを続けたいとした。

両社は昨年12月23日、新たに共同で持ち株会社を設立する検討に入ると発表。新会社の社長についてはホンダが指名する取締役から選定し、社内・社外取締役の過半数も同社が指名するなどホンダ主導の色彩が強かった。両社は統合準備委員会で協議を進めてきたが、当初は1月末をめどとしていた協議の方向性を発表する時期は2月中旬に延期され、破談の見通しが高まっていた。
次の協業先
こうした中、日産はすでに新たなパートナシップ探しを始め、1カ月以内に詳細を発表すると明らかにした。事情に詳しい関係者によると、日産にとって最も重要な市場である米国や自動車にとっても重要性を増している情報通信(IT)関連の分野の企業などは有力な候補になり得るという。
台湾の鴻海精密工業の劉揚偉会長は日産との提携に必要であれば、仏ルノーが保有する日産株を買い取ることを検討し得ると、12日に台北で語った。ルノーからの日産株購入はゴールではなく協力だと説明。鴻海がホンダや日産と会合を持ったことを明らかにした。これに対してホンダの三部社長は鴻海と議論したことはないと否定。日産の内田社長も鴻海とマネージメントレベルで話していないと述べた。
また、米投資ファンドのKKRが日産の資金調達に関して初期段階の協議を始めていることも明らかになっている。協議は初期段階で、現時点では具体的な資金調達の規模や方法についての議論には入っていないという。
英調査会社ペラム・スミザーズ・アソシエイツのアナリスト、ジュリー・ブート氏はリポートで、米アップルの電気自動車プロジェクトや米配車サービスのウーバー・テクノロジーズによる自動運転部門売却などの例を挙げた上で、将来の自動車の価値はソフトウエアにあることを考えると、「テクノロジー企業がレガシー自動車メーカーを買収し、支援することに興味を示す理由を見いだすのは難しい」との見方を示した。
その上で、たとえそういった企業が多少の興味があったとしてもホンダよりも提示価格は悪くなる可能性が高く、「日産は長期的な存続に不可欠ではないとみなされる資産を全て迅速に切り離すことになるだろう」とした。
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.