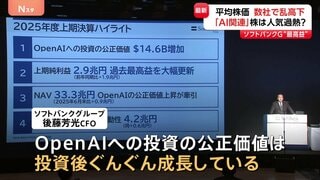(ブルームバーグ):多様性・公平性・包摂性(DEI)プログラムを導入している米企業に対し、保守派がこれを縮小するよう圧力を強めている。主戦場となるのは各社の年次株主総会だ。
何らかの運動を展開するグループは株主提案をてこに、取締役会に影響力を及ぼそうとすることが多い。宗教団体や人工妊娠中絶の権利活動家、環境保護を訴える人々、コーポレートガバナンス(企業統治)運動家は米国で毎年、何百もの議案を提出している。
トランプ米大統領の復帰で勢いづく右派団体は今年、アップルやマクドナルド、コカ・コーラなど十数社の米大手企業にDEIプログラムを再考するよう、株主提案で圧力をかけることを計画している。
ウォルマートは株主投票にかけずにDEI政策の一部を撤回。一方、今月23日に開かれたコストコホールセールの株主総会では、反DEIの議案が否決されるなど、踏みとどまる企業もある。JPモルガン・チェースやゴールドマン・サックス・グループは、DEIの取り組みを後退させることはないと表明した。

株主提案とは
従業員の多様性や役員報酬、気候変動などに関して、株主が会社側の対応を望む場合、年次株主総会で議案を提出する。
少なくとも3年間、2000ドル(約31万円)以上の株式を保有している株主は、議案を提出し、株主総会の投票用紙にこれを記載させることができる。
その後どうなるか
採決に持ち込めたとしても大半の議案は否決される。経営陣が議案を覆させるため、投票に至らないことも多い。そのためには、経営陣はその議案が日常的な事業運営を妨げるものだと規制当局を納得させる必要がある。要求の一部を実行する代わりに、議案を取り下げるよう投資家を説得することもある。
議案が採決にかけられる場合、提案者は株主総会で他の株主に対して数分間発言し、賛同を得ようとする。会社側は否決するよう推奨することがほとんどだ。
株主総会は民主主義ではなく、議案が可決されても拘束力はない。だが、会社側は株主の要請に何らかの形で応えることが多い。ブラックロックが2021年に公表した調査によると、30-50%相当の株主の支持を得た議案のうち、約3分の2は企業が投資家の要望に全面的、または部分的に応える結果となった。50%を超える支持を得た議案の大半については、結果的に企業が完全に従っている。
株主提案は一般的になりつつあるのか
ブルームバーグ・インテリジェンスによると、24年の株主総会シーズン(公式には6月から翌年6月までだが、大半は4-6月に開催)には、時価総額上位3000社の米企業に対し、過去最高となる665件の議案が提出された。
21年には、バイデン政権下の米証券取引委員会(SEC)が環境・社会問題を中心とした議案をより多く提出するよう株主に門戸を開いた。
株主提案は真の変化をもたらすか
投資家のキャンペーンによって最近、人工知能(AI)の適切な使用に関して行動を改める企業も現れた。ウォルト・ディズニーとコムキャストがAI利用を巡り追加情報の開示に同意したと報じられた後、労働総同盟産別会議(AFL・CIO)は両社に対するAIに関連した株主提案の取り下げを発表。アルファベットとメタ・プラットフォームズも今年、AI関連の提案に直面する。
それ以前の応酬では、結果的に会社側が少なくとも3年ごとに役員報酬パッケージを巡って採決し、より頻繁な採決が必要かどうか株主が決定できるようになったケースもある。こうした取り組みで、役員の退職金に関してより多くの情報も公表されることになった。
株主提案により、株式の大部分を保有しなくてもオーナーが会社をコントロールできる特別議決権株式を廃止した企業もある。また、会長と最高経営責任者(CEO)の役割を分離するよう会社側に迫った提案もある。
株主提案の歴史
社会問題に基づく株主提案は、1970年代前半に米ゼネラル・モーターズ(GM)に対して出されたものが始まりで、当時アパルトヘイト下にあった南アフリカ共和国での事業停止を求めるものだった。この時は失敗に終わったが、南アフリカにおけるGMの役割について、投資家と同社の間で議論が活発化。それから約15年後、GMは南アフリカから撤退した。
男女間の賃金格差や労働における人種差別、温室効果ガス排出への対処に関する提案の数は、「#MeToo」や「ブラック・ライブズ・マター(黒人の命も大切だ)」、気候変動を巡る運動をきっかけに爆発的に増加。その後、保守的なグループが独自の議案を提出し始め、会社側にDEIの取り組みを縮小するよう求めた。ブルームバーグ・インテリジェンスのデータによれば、24年の株主総会シーズンには、反ESG議案が60%増えた。
原題:Anti-DEI Groups Target Companies Using Proxy Votes: QuickTake(抜粋)
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.