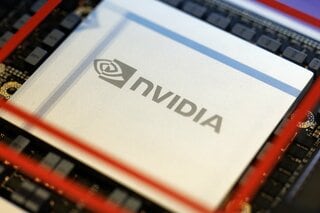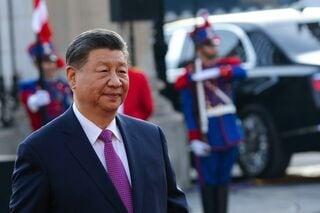バレンタインデーにおける女性会社員の行動の変遷~新聞記事調査より~
1986年から1989年~「義理チョコ」定着期~
義理チョコは、職場の男女格差が大きい時代に女性会社員たちが何とか適応しようとした行動の一環だったと考えられるが、その後はどのように変遷していったのだろうか。
バレンタインチョコレートの贈答対象の推移に関する公表調査が無いため、ここからは、バレンタイン商戦について報じる新聞記事を中期的に調査し、女性の贈答行動の変遷を分析する。
新聞記事には、小売店が取りそろえた商品の特徴や、売り場担当者による見立て、買い物客自身の購買行動やコメントなどが盛り込まれており、そのときどきの特徴を掴むことができるからである。
なお、贈答の構図に関しては、後に紹介するように、「本命」の他、友人に贈るパターンや、男性から女性に贈るパターンなど様々なものがあるが、本稿は、女性会社員と男性の上司や同僚との関係性に注目することから、主に「義理チョコ」と自分用チョコの比重に着目して分析する。
また調査対象時期は、均等法施行後の変遷をたどるため、施行年の1986年から最新の2024年までとする。
具体的には、新聞記事検索サービス「日経テレコン」を用いて、全国紙5紙(読売、朝日、毎日、日経、産経)の、1986年から2024年までのそれぞれ1月1日から2月14日に掲載された、「バレンタイン」というキーワードを含む記事を抽出し、約10年ごとにその特徴を分析する。
始めに、1986年と翌1987年のバレンタインの時期の新聞記事を検索すると、関連記事の本数が少なく、内容も「義理チョコ」や「本命」などという、贈答対象に関する記述が殆ど見られない。
バレンタインデーにチョコレートを贈答する習慣ができたのは1950年代からと言われるが、「義理チョコ」という贈答スタイルが、日本にまだ定着していなかった可能性がある。
1988年には、初めて「義理チョコ」に関する記事が登場する。
1998年2月13日付読売新聞は、日本のバレンタイン商戦の始まりについて「本格的には、さる(昭和)三十三年、都内のメーカーがデパートと一緒にバレンタインセールと銘打ってスタートした」と紹介した上で、「数年前から、職場の男性や友人、知人にもこの日に『義理チョコ』を配る習慣が広まってからこの時期の売り上げは年々一割以上も伸びる勢いになった」と解説している。
この記事の通りだと、職場で「義理チョコ」の習慣が広まったのは均等法施行年(1986年)前後で、その後、義理チョコが広まり、チョコレートの売り上げ自体を押し上げてきたと言えそうだ。
1988年2月8日の日本経済新聞も、バレンタインを「海外の習わしがイベントに定着した“成功例”」と評し、「最近は、安いチョコレートは複数の男性に配り、本命には、ネクタイ、洋酒、システム手帳など高価なものを贈り始めた」と記述しており、「義理チョコ」と「本命」を棲み分ける贈答習慣について解説している。市場規模は「チョコ四百億円を含めて一千億円市場」としている。
1989年1月29日の読売新聞には、東武百貨店池袋店が、同店に勤める女性200人を対象にした意識調査の結果が紹介され、「買うチョコレートは六個で、費用は約四千三百円(現在の物価で約5,200円)」と記述されていた。
また1989年2月12日の日本経済新聞には、「マンデー日経」の女性読者142人へのアンケート結果が掲載され、「チョコをあげたくない相手」は「お礼の一言もない」がトップになっていた。
つまり、義理チョコがお礼やお返しを前提とした行為になっていたということが、このアンケート結果からも分かる。
また、各紙の地方版でもバレンタイン商戦が熱を帯びている様子が報じられており、イベントの定着が伺える。
1990年代~「義理チョコ」最盛・抵抗期~
1990年代初頭は、バブル景気と円高の影響などで、海外の輸入チョコレートが増え、「本命は高級品、義理はお手頃」という贈答対象による二極化が鮮明になってくる。
しかし、好景気の影響からか、義理チョコについても個数の増加傾向がうかがえる。
1990年2月2日の日本経済新聞は、洋菓子メーカーの老舗、モロゾフが、東京都内に勤める課長・係長を中心とする“中年サラリーマン”に行った調査結果として、男性が「昨年もらったチョコレートは平均5.2個だったが、今年は5.8個を期待」と紹介しており、義理チョコが増加傾向であることが伺える。
また、1991年2月13日の毎日新聞は「本命くんも義理チョコ氏も『3倍返しが常識』」と、当時の義理チョコのお返しにまつわる習慣を分析している。
小田急百貨店新宿店のバレンタイン商戦に来た東京都目黒区のOL(25)の声として「義理チョコだからこそ、ホワイトデーにはきちんと義理を果たしてほしい。忙しくて返し損ねたなんて言ったら、男の値打ちを落とす」と紹介。
この記事では、旅行代理店課長(40)の「義理チョコをもらったり、ホワイトデーでお返しをするのも上司と部下の一種のコミュニケーション」という声も紹介されており、女性からの「贈答」と男性上司からの「返礼」という、職場でチョコレートを介したコミュニケーションが完成していたことが示されている。
1990年代半ばからは、バブル崩壊や阪神大震災などの影響もあり、「義理チョコ不要論」が見られるようになる。
1994年のバレンタイン時期の各紙は概ね「不況にも関わらずバレンタイン商戦は好調」といったトーンの記事が多いものの、一部では異論が唱えられている。
1994年2月13日の朝日新聞は、バレンタインの贈り物について「不要(16%)が必要(7%)を上回った」という大手通販・千趣会によるアンケート結果を紹介している。
1994年2月12日の読売新聞は、男性と思われる大手生保会社の課長(43)の“ぼやき”として「毎年、1万5、6千円は飛んでいく。チョコなんか食べたくないし、換金もできないのに」という男性側からの不要論を掲載している。
また、1995年2月10日の朝日新聞は、義理チョコを禁止する企業が出てきていることを紹介している。
1990年代終わり頃には、義理チョコの減少傾向が伝えられている。
1998年2月13日朝日新聞は「一人あたりの購入数はバブルのころに比べ大幅に減っている。不況でOLも『義理チョコ』の贈り先を厳選しているようだ」と解説している。
ただしこの時期までは、小売りにとっては、義理チョコが依然、バレンタイン商戦の主要な収入源となっているようで、1998年2月7日の読売新聞は「職場の上司や同僚などに渡す『義理チョコ』はひところより減っているものの、売り上げの半分以上を占めている」と記述し、各百貨店が義理チョコ販売を伸ばそうと知恵を絞る様子を紹介している。
2000年代~「義理チョコ」形式化・「ご褒美チョコ」定着期~
2000年代の各紙を展望すると、義理チョコが次第に形式化し、減少傾向がみられるのと同時並行して、売り場に増え始めた海外の高級チョコレートを、女性が自分用に“ご褒美”として購入する現象が次第に大きくなっていく傾向が確認できる。
2000年2月7日の産経新聞は、商社勤務女性の投稿記事として、依然、職場の伝統である義理チョコの購入を続けているが、「時代の流れ」として、「チョコ一個で約200円から300円と、単価は著しく低下している。
以前は込み合うデパートの地下に行列したものだが、今ではバレンタインの二、三日前に会社にやって来る業者でまとめ買い」していると記述されており、女性が義理チョコ購入にかける金銭的・時間的コストの節約ぶりを伝えている。
このように存在感が低下していく義理チョコと入れ替わるように台頭してくるのが、自分用のご褒美チョコだ。
2005年1月30日の産経新聞は、「ここ数年、働く女性を中心に“ご褒美需要”の高まりが顕著になっていきている」と解説。
東急百貨店広報の話として「『手の届く贅沢な物』を自分の“慰労”のために買うという行動」で、「昨年のクリスマス商戦では、アクセサリーやブランド物のバッグを『自分用に』と買っていく女性客の姿が目立った」と紹介。
働く女性が「がんばった自分」へのプレゼントとして、積極的に購入していく様子を紹介している。
2010年代~「義理チョコ」衰退・「ご褒美チョコ」発展期~
2010年代以降は、「義理チョコ」が一層、下火となったためか、義理チョコに言及する記事自体が少ない。
対照的に、自分用のご褒美チョコが高級化している他、友達と交換し合う「友チョコ」が拡大したり、男性から女性に贈る「逆チョコ」が生まれたりし、贈答構図が多様化していることが示されている。
2014年2月12日の読売新聞は、売り場を訪れた女性会社員(25)の「職場用に生チョコを30個ほど作るつもり。女性社員が持ち寄って食べ比べる予定です」という声を紹介し、職場で義理チョコよりも友チョコが主流となっている状況を紹介している。
同年2月8日読売新聞香川版でも、「友チョコ」ニーズを意識して、クマやハート、ディズニーキャラクターなどをあしらった商品を多く取り入れたという高松三越の状況を紹介している。
一方、自分用のご褒美チョコは、景気の回復傾向もあって高級志向が進んでいることが伺える。
2018年1月26日の読売新聞徳島版は、百貨店が普段は扱っていない海外の人気商品を取りそろえ、仕事帰りの女性らによく売れている、と紹介している。
2018年には、義理チョコの衰退傾向に追い打ちをかけるように、高級チョコレートブランド・ゴディバが「日本は、義理チョコをやめよう」というキャッチコピーの新聞広告が掲載されたことが、朝日新聞や毎日新聞で取り上げられた。同年2月10日の朝日新聞では《バレンタインデーは嫌いだ、という女性がいます》《義理チョコを誰にあげるかを考えたり、準備をしたりするのがあまりにもタイヘンだから、というのです》と広告の宣伝文句を紹介。
「本当によく言ってくれたと思います」という女性会社員(37)の声も添えている。
2020年~2024年 「義理チョコ」衰退・「チョコ好きの祭典」発展期~
2020年代に入ると、コロナ禍による出社減少や接触回避の動きが義理チョコ衰退を加速した一方、巣ごもり需要などで、自分用チョコがさらに高額化する傾向が見られる。
かつては義理チョコに差をつけていた「本命」を抑えて、現在は「自分用」の予算がトップに立っているという調査結果も見られる。
さらに、コロナ禍が明けて初となった2024年のバレンタイン商戦では、売り場の来場者向けの演出がエスカレートし、バレンタインデーは、さながら「チョコ好きが楽しむ祭典」に変貌しつつある。
全国に外出制限が出されて初めて迎えた2021年のバレンタイン商戦では、かつて主流だった義理チョコはさらに衰退が進んだことと、普段は外出を我慢しているので、予算をかけて“おうち時間”を楽しみたいという動機から、自分用チョコがより高額化していることを伝える記事が多い。
2021年2月10日の毎日新聞は、「コロナ感染防止で在宅勤務が進み、食べ物の共有を制限する企業もある」と記述し、「取引先や仲の良い上司に個人的に渡していたが、今年はやめる」(食品会社)という女性会社員と思われる声を紹介。
2021年2月12日の読売新聞群馬版は、高崎高島屋で、付加価値の高いチョコレートに人気が集まっていることを紹介し、「テレワークの普及などで義理チョコ需要は減ったが、外出自粛を求められるなか、頑張る自分用として買い求める人が増えている」というシニアマネージャーの分析を掲載している。
新型コロナウイルスが5類移行後初となった2024年のバレンタイン時期の各紙を見ると、売り場は活況を取り戻したようだが、義理チョコ需要の回復は見られない。
代わって売り場では、イートインやシェフによる実演販売など、来場者自身が楽しめるような演出が進化している。
2024年2月9日の毎日新聞福岡版は、「地元産の素材を使ったチョコを売り出したり、パティシエが来場してふれ合う機会を設けたりするなど特別感を打ち出している」と報告し、2月10日の読売新聞埼玉版も、伊勢丹浦和店で「パティシエの作業をガラス越しに見ることができ、それをスマートフォンで撮影する人も多い」と紹介している。
また、2024年1月25日の読売新聞は、女性誌「婦人画報」を発行するハースト婦人画報社が約4,000人を対象に行った調査結果として、自分用にチョコレートを購入するという回答が前年より4ポイント高い61%となり、予算も「自分用」(3,352円)が「本命」(3,131円)を上回ったことを紹介している。
2024年2月9日の朝日新聞も、JR名古屋高島屋が約2,700人に行った意識調査の結果、回答者の半分がバレンタインの楽しみ方を「自分へのご褒美」とし、自分用の予算は、3割近くが「金額は気にしない」と高額化していることを伝えている。