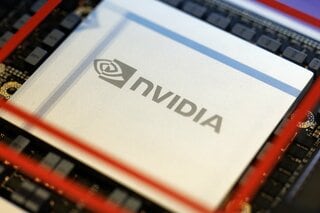バレンタインデーにおける働く女性たちの行動が変遷している。
2000年頃までは職場の習慣になっていた「義理チョコ」が下火となり、自身のために好きなチョコを購入して楽しむスタイルが主流となってきた。
これには、景気変動や贈り物に関する意識の変化など、様々な要因が関連していると考えられるが、背景には女性のキャリアの変化があるのではないだろうか。
はじめに
働く女性たちの贈答行為の変化には、景気変動や贈り物に関する意識の変化、ハラスメント意識の高揚、コロナ禍における行動制限など、様々な要因が関連していると考えられるが、「職場の女性から男性へ」という図式そのものが薄れた背景には、女性のキャリアの変化があるのではないだろうか。
そのような関連について考察するために、本稿ではまず、男女雇用機会均等法(以後、「均等法」)施行後の「OL」たちの意識と行動を描写した先行研究のレビューから、「OL」にとって「義理チョコ」を贈答する意味や役割を明らかにする。
そして、その後のバレンタインデーの贈答行為の変化について、各年のバレンタイン商戦の様子を伝える新聞記事の内容を中期的に調査し、分析する。
最後に、1980年代から現在までの女性のキャリアの変化を確認し、バレンタインチョコレートの贈答行為の変化との関連について考察する。
「義理チョコ」の意味と役割~OLたちの職場での「構造的劣位」と適応~
「義理チョコ」贈答役を担う「OL」の誕生と増加
まず、働く女性にとって「義理チョコ」が果たす役割について考える前に、義理チョコが誕生・普及した背景から概観する。
そもそも義理チョコが普及するためには、贈答役である女性会社員が存在することが前提である。
昨年公表した筆者のコラム「元祖『OL』たちは令和で管理職になれるか」(研究員の眼)でも紹介したが、日本では高度成長期以降、産業構造の変化によって事務仕事が増加し、それに伴って、雇用で働く女性も急増した。
そのような中で、職場で働く女性を称する「OL (Office Lady)」という和製英語も誕生した。
統計上も、女性事務職の人数は1953年には127万人だったが、2010年には777万人に増加している。
このように、戦後、事務仕事の拡大に伴って増加していった「OL」が、日本独特の「義理チョコ」文化を生み出し、普及させていった。
「OL」にとっての「義理チョコ」~先行研究のレビューより~
次に、義理チョコの意味と役割を明らかにするために、前述した筆者のコラムでも取り上げた、小笠原祐子氏著『OLたちの<レジスタンス>』(1998年、中公新書)の中から、「OL」とバレンタインデーに関する分析をレビューする。
なお、同書の内容に関する説明には、筆者の解釈が含まれていることを、あらかじめお断りしたい。
また、「OL」という用語は、現在では死語だと思うが、同書のレビューの際には、便宜上、用いることとする。
同書で小笠原氏は、聞き取り調査などを基に、均等法施行後のOLたちの職場での行動をリアルに描いた。
それによると、当時のOLたちは、結婚・出産退職による短期雇用が想定されていたため、会社では昇進・昇給も殆ど無く、出世競争の蚊帳の外に置かれていた。
頑張って仕事をしても、しなくても、どうせ考課には反映されないので、予め決まった仕事以上のことを頼まれたら、それに応えるかどうかは「サービス」という感覚だった、と説明している。
そのようなOLたちにとって、年に一度のバレンタインデーで、男性の上司や同僚に贈るチョコレートは、自発的な“贈答品”という恰好を取りながら、その実、相手によってモノや贈り方に差をつけることで、普段のうっぷんを晴らしたり、感謝の気持ちを表したりする絶好の手段になっていた。
例えば、職場のほとんどの男性社員に対しては、OL1人から1個ずつチョコレートを渡すのに、嫌いな上司には、OL同士が相談の上、3人から1個にして総数を減らしたり、わざと渡す時間を遅らせて不安にさせたりと、相手によって差をつけて、反応を楽しむことがあったという。
中には、包装の上から指でぼこぼこに押して、こなごなにしたチョコレートを渡した事例もあったというのだ。
その結果、日本のような仕切りの無い大部屋の職場環境では、人気のある男性社員とない男性社員の差が一目瞭然になった。
「人気のある男性には、それこそ大きな段ボール箱をも埋め尽くすかと思われるほどのチョコレートが来たりするのに、人気のない男性には、超義理チョコという感じのチョコレートが数個来るだけ」と同書は描写している。
このように書くと「OLは怖い」と感じる男性もいるかもしれないが、これらの行動は、職場でのOLたちの立場の弱さ、すなわち「構造的劣位」から生じていると小笠原氏は分析している。
その行動の特徴として、小笠原氏は「匿名性」と「多義性」という2点を指摘し、それらは、社会的弱者が「抵抗」のメッセージを隠ぺいするために用いられる手段だと説明している。
すなわち、ある男性社員が受け取るチョコレートの総数が少なくても、その判断は、職場のOLたちの“意思の総和”として現れたものであるため、特定のOLの責任にすることができないということ(=「匿名性」)。
また、OLたちがたとえチョコレートに復讐の気持ちを込めていても、あるいは感謝や愛情をこめていても、表面上は同じ媒体(チョコレート)であるため、男性側からは、本音を特定できないということ(=多義性)だ。
このように、敵意または好意をチョコレートの中に包み隠し、あえて曖昧さを残したまま、相手に手渡しているのだ。
小笠原氏の分析を改めてまとめると、会社から短期雇用を想定されているOLたちは、普段、仕事の成果を期待も評価もされない弱者の立場にある。
自分たちの力ではその状況を変えることはできない。でも本当は、もっと一人ひとりを尊重してほしい。
また、お返しなどを通して具体的に表現してほしい――。
そのような思いが表出したものが義理チョコだと言える。
これらの分析から、義理チョコという日本独自の習慣が生まれた背景には、職場の大きな男女格差と、OLたちがその事実を受け止めた上で、職場に適応し、自分なりに楽しもうとする内発的動機があったと言える。
言い換えれば、ジェンダーギャップの大きい職場だからこそ、OLたちによる贈答イベントが生まれる必然性があったのだ。
そこに、製菓業界や小売りが売り込んだバレンタインデーというフレームが合致した。
つまり、組織風土に限界を抱える中で、OLたちが、何とか自分たちに有利な状況を引き出そうとするアピールが、義理チョコという形に昇華されたと言えるのではないだろうか。