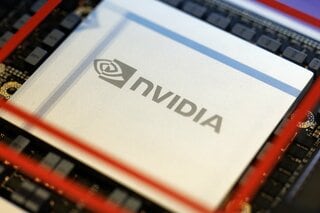(ブルームバーグ):約1年前に中国で最も注目を集めたテクノロジー製品といえば、「DeepSeek」の人工知能(AI)モデルだった。2026年に最も話題となっている製品は、はるかにシンプルなもので、「孤独死」を心配する人々のためのアプリだ。
「死了么(死んだか?)」という露骨な名称の生存確認アプリは、中国のアプリストアでチャート首位に躍り出た後、世界中に拡散した。インターフェースは驚くほどシンプルだ。主に独り暮らしの利用者が、生きていることを確認するためにタップする。2日連続でタップがなければ、緊急連絡先に通知が届く仕組みだ。
刺激的な名称もさることながら、このアプリが広告費を一切かけずに爆発的に拡散し、しかも流行のAI製品を装う必要すらなかったことには理由がある。婚姻件数が減少し離婚率が上昇する中国で、出生率が過去最低を記録した時期と重なったのだ。
多くの人は、このアプリが自立した生活を維持しようとする高齢者向けに開発されたと思い込んでいた。しかし実際は、都市部での孤立した生活という自らの体験から着想を得たものだったと、Z世代の開発チームはインタビューで述べている。中国では単身世帯が30年までに2億世帯に増加すると予想されている。
こうした人口動態の変化は現代中国に特有のものではないが、当局が今、このような形で注目されることを望んでいないのは確かだ。このアプリは最近、中国のアプリストアから静かに削除された。中国では死を率直に口にすることはタブーで不吉とされ、アプリの開発者らは、ブランド名の変更を計画していると微博(ウェイボー)への投稿で明かした。新しい国際的な名称「Demumu(デムム)」は、世界的に人気のキャラクター「Labubu(ラブブ)」風に「death(死)」をもじったものだ。しかし期待されたほど浸透せず、開発者らは現在、SNSを通じて新しい名前のアイデアを募っている。
「メメント・モリ」
中国当局を逆なでし、世界に波紋を広げたとはいえ、この製品のコンセプトは悔しいほど秀逸だ。自分が思いつかなかったことが悔やまれるほどだ。大手テック企業やスタートアップがこぞって次のヒットAIアプリを開発しようと競う中、実際のユーザーが最もよく口にする不満は、こうしたツールの多くが、問題を見つけようとするソリューションであることだ。友人からの2行のメッセージを要約してもらう必要はなく、基本的な人間関係にソフトウエアが介入してくると、便利というより煩わしく感じることもある。
「死んだか?」はその真逆を行く。気の利いたことをしようとせず、純粋に実用的だ。独り暮らしの人々にささやかな安心感を提供する。たとえその存在自体が、深刻化する孤独のまん延を浮き彫りにしているとしてもだ。人気のフードデリバリーアプリ「餓了麼(おなかすいた?)」をダークにもじったこの名称は、競争社会を嫌う「寝そべり族」と呼ばれるZ世代のニヒリスティックなユーモアを体現している。ネット上では、多くの中国の若者がこのアプリを不謹慎とは捉えず、一種の「メメント・モリ(『死を忘れるな』という警句)」と受け止めている。
生活のより多くの場面にAIを組み込もうとする動きが注目を集めるのは当然だ。しかしアジアをはじめ世界各地で、高齢者向けテクノロジーは今後急成長が見込まれる分野でもある。中国当局は、高齢者の購買力向上や新しいデジタルプラットフォームへの適応意欲を挙げ、「銀髪経済(シルバー経済)」を将来の成長エンジンと位置づけている。政府は、こうしたイノベーションや、それが提起する不都合な問いを抑え込むのではなく、これらのツールを歓迎すべきだろう。
全米退職者協会(AARP)の予測によると、米国では高齢者のテクノロジー向け支出が30年までに1200億ドル(約18兆4000億円)に達する見通しだ。一方で、50歳以上の人の59%が、こうしたテクノロジーは自分たちの年齢層を念頭に設計されていないと感じている。開発者にとって、この市場を開拓し、そのギャップを埋める世界的なビジネスチャンスは膨らむ一方だ。
「つながり」を求める
しかし、このアプリの拡散が引き起こしたより深い議論は、業界にとってさらに対処が難しいものだ。テクノロジーは私たちをより孤独にしているのか、それとも孤独を和らげているのか。世界的に見て、SNSは対面での交流を避けることをはるかに容易にした。中国では、スーパーアプリがあらゆることを最適化し、配車や食事・日用品の注文に際して、実際の人間と一言も交わす必要がなくなった。そしてAI覇権を目指す競争の中で、人々は過酷な(そして厳密には違法な)「996」文化(午前9時から午後9時まで週6日働く文化)に突き動かされ、家を離れる時間を増やしながら長時間働いている。
DeepSeekの躍進が中国テック業界の華々しい瞬間だったとすれば、「死んだか?」は二日酔いのようなものだ。この飾り気のない生存確認アプリがランキング首位に躍り出たのは、優れたエンジニアリングのおかげではない。人口動態や社会の不安をプッシュ通知という形に変換したため拡散したのだ。当局がアプリストアから削除しても、開発者が「death」をラブブ風にアレンジしようとしても、このアプリが露呈させた「つながり」への根源的な需要が消えることはない。
これはAI業界への警鐘でもある。次のヒット製品は、おそらく私たちの会話を要約するものではないだろう。なぜ私たちの会話が減っているのかに向き合うものになるはずだ。機械をより人間らしくする競争の中で、中国で今年最初にブレークしたアプリは、「まだ生きていますか」と問いかけるだけだ。
(キャサリン・トーベック氏はアジアのテクノロジー分野を担当するブルームバーグ・オピニオンのコラムニストです。CNNとABCニュースの記者としてもテクノロジーを担当しました。このコラムの内容は、必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)
原題:Dying Alone Is China’s Latest Tech Fixation: Catherine Thorbecke(抜粋)
もっと読むにはこちら bloomberg.com/jp
©2026 Bloomberg L.P.