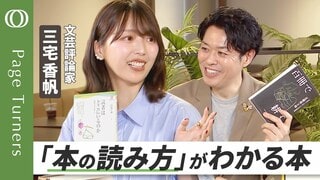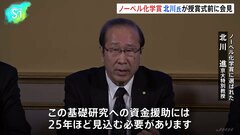EVは環境に優しいのか?
そしてもう一つのEVの見方に対する変化は環境負荷です。これまでEVへのシフトの大きなドライバーは環境負荷の低減でした。確かにガソリンを燃焼しないEVは走行時にCO₂は排出しません。しかし、直近ではより広範にCO₂排出量を計測し抑制することが求められています。EVの場合は、バッテリー製造時のCO₂排出量が大きくガソリン車に比べ生産時のCO₂排出量は増加します。また走行に必要な電気もソーラーなどの再生可能エネルギーを使用するか、石炭などの火力発電を使用するかでCO₂の排出量が大きく変わってきます。
一部の調査によると製造から13年、10万キロ走行した場合の累計でのCO₂排出量は、再生可能エネルギーの普及が進んでいる欧州の国などではハイブリッド車(HV)に比べEVの方が少ないものの、東南アジアの国などの火力発電の電力構成が高い地域ではHVの方が優位になるとの試算もあります。
また私はEVの寿命に対しても懸念を持っています。中国では既にEVが家電のように短いサイクルで乗り換えられEVの墓場と言われる廃車置き場も出現しているようです。またデータはまだ少ないものの、日本における中古車市場をみても、EVの場合はガソリン車以上に、ある程度の年式となると中古車市場において台数が急減する傾向があります。これはガソリン車よりも早いタイミングで車両としての価値が棄損し廃車となっている可能性を示唆しています。EVではバッテリーが原価に占める割合が重く、バッテリーが劣化することがその背景とみられ、環境負荷低減にはバッテリーの性能向上やリサイクル体制の構築も不可欠です。
日系自動車メーカーはEVだけに注力する方針ではなく、地域に応じて最適な動力源(パワートレイン)を提供するマルチパスウェイ戦略を取っています。かつてはEVに注力しないことがリスクと株式市場ではみられていましたが、地域によって最適なパワートレインは異なるとの見方が広がりつつあることから、日系自動車メーカーの戦略は再評価されています。しかし日系自動車メーカーは多様なパワートレインで性能、コストともに競争力を維持していくことが求められると予想され、各企業の取り組みの違いによって競争力の差がますます大きくなると考えます。各地域においてパワートレイン比率は異なるペースで変化し、そのなかで、既存メーカー、新興メーカーがどのようにシェアを分け合っていくのか、技術動向や各国の政策など複雑な要素が絡まりアナリストにとっては予測することが非常にチャレンジングな環境となっていますが、地道な調査活動を通じて投資機会の発掘に努めたいと思っています。
(※情報提供、記事執筆: ニッセイアセットマネジメント 投資調査室 鈴木衡大朗)