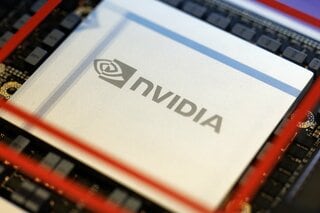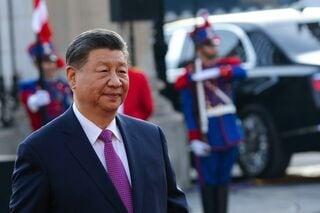それでは、もし主婦の家事育児負担が軽減されたら、働き方への意識はどう変わるだろうか。主婦層に特化した人材サービス会社が運営する調査機関「しゅふJOB総研」が今年9月、主婦(主夫)ら460人を対象に行ったインターネット調査によると、「いま最も望ましいと思う雇用形態」は、パートなどの「短時間非正規社員」が35.4%となってトップだった。これに対し、「仕事に専念できるなら、最も望ましい雇用形態」を尋ねたところ、トップは「フルタイム正社員」の43.3%となり、順位が入れ替わり、割合も大幅に上昇した。つまり、時間の制約があって今は短時間の非正規雇用を希望しているが、もし制約がなくなり、自分が働きたいだけ働けるなら、正社員を選択する主婦(主夫)が増える可能性があるということだ。同社の求人サイトに登録する。


従って、現在、短時間で働いている主婦の就労時間を増やし、人手不足緩和や女性の所得向上に結び付けるためには、「年収の壁」を上方にスライドするだけではなく、夫婦の家事育児分担を見直さなければならないということだ。ただし、現在、日本人男性の家事育児時間が短い背景には、日本人男性が世界的にみて長時間労働だという日本企業の働き方の問題もあるため、男女役割分業意識を見直すためには、働き方自体も見直す必要がある。
さらに付け加えるなら、女性の就労の壁を巡るより本質的な問題は、日本では約30年前から共働き世帯が多数派となっているにも関わらず、夫が妻を養うことを前提とした税・社会保障制度が温存されていることにある。配偶者控除や、「106万円」、「130万円」以下の年収で働く人への社会保険料免除、民間企業の配偶者手当などは、妻が被扶養であることにインセンティブを与えるものであり、男女の賃金格差を助長していると言える。
個人の立場から見ると、配偶者控除や扶養などは、既に生活設計に組み込まれているため、急激な制度変更は難しいが、人手不足解消やジェンダーギャップ解消のためには、中期的に見直していくべきだろう。女性の就労時間を増やし、年収水準を上げることは、女性自身の老後の暮らしを守るためにも大変重要だ。
公的年金に関して言えば、非常にゆっくりとしたペースだが、働く女性の増加という時代変化に合わせて、方向転換しつつある。例えば、夫と死別した妻に給付される遺族厚生年金を巡り、現行制度では妻が30歳未満の場合のみ5年間の有期給付(30歳以上であれば終身)とされているルールを、段階的に有期給付とする年齢下限を引き上げていくことが、現在、厚生労働省の審議会で検討されている。この動向と同じように、今回の「103万円の壁」の引き上げについても、単に「103万円を超えて働く人を増やすため」ということではなく、ジェンダー平等や女性の所得向上、それらによる経済成長を目指した、税・社会保障制度の一体的改革を加速するための一歩だと位置付けられることを期待したい。
政府は、「年収の壁」を103万円から178万円まで引き上げると、国と地方を合わせて7~8兆円の税収減になると試算している。この「税収マイナス7~8兆円」が、単に、国民民主党の国会での協力を得るためという“少数与党の政権運営コスト”とならないように、この改正によってどういった社会を目指すのか、旗印を示してほしい。
(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子)