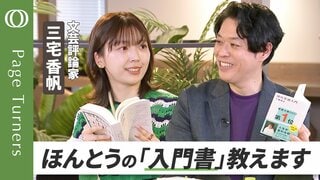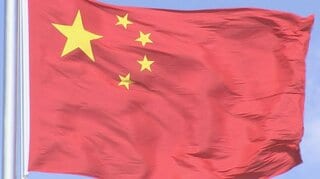衆院選の結果と影響をどうみるか?~財政拡張と金融政策ニュートラルは既定路線か
10月27日投開票の衆院選については、自民党が無所属で当選した議員を追加公認することなどによってギリギリで自公過半数が確保できると、筆者は予想している。しかし、その場合でも25年夏の参院選に向けた不安が残るため、年末に策定される見込みの経済対策(補正予算)は比較的大きなものとなるだろう。
青木官房副長官は10月16日に昨年の経済対策が補正予算13兆円、事業規模37兆円程度であったことに触れつつ、今回の経済対策について、昨年を上回る規模としていく予定であることを示唆した。いわゆる「真水」にあたる歳出増の規模が13兆円超になるか、乗数効果の大きい政策が重視されて事業規模だけが昨年の経済対策を超えるのか現状では不明だが、財政拡張的であることは間違いないだろう。
経済対策のメニューについては、電気代・ガス代・ガソリン代の補助策の延長に加えて地方創生臨時交付金の活用が想定される。すでに石破首相は現状では当初予算で1,000億円計上されている地方創生の交付金を倍増させる方針を表明している。地方創生の交付金は当初予算ベースでは少額だが、過去の政権は20年に創設した「地方創生臨時交付金」として地方自治体に18兆円超を交付してきた。むろん、コロナ対応で必要だった面もあるが、岸田政権ではインフレ対応のバラマキとしても活用されたという批判も多い。石破政権でも同様の手法によって地方自治体を介したバラマキが行われる可能性が高い。この交付金を使って成長力を高めている自治体もあるかもしれないが、多くの自治体ではキャッシュレス決済のポイント還元などといった短期的な個人消費や中小企業の支援策になっているとみられる。いずれにせよ、このような政策は岸田政権でも行われてきたことから、これが継続することで新たな経済効果が出てくると考えることはできない。
なお、筆者の予想が外れて自公過半数割れとなった場合でも財政拡張路線が強まることに変わりはないだろう。例えば、連立政権入りが指摘されている日本維新の会や国民民主党も財政拡張を主張している。自民党内で石破降ろしとなれば、高市氏が新総裁の候補となるが、高市氏は財政拡張を主張するだろう。
金融政策についても同様である。岸田前首相は円安によるインフレ高進の影響を緩和するため、日銀に利上げを促したと言われている。7-8月には円高が進んだものの、足元では再び円安圧力が強くなっている。この状況で金融緩和の必要性を訴えることは、支持率を引き上げる上で得策とは言えない。一方で、金融引き締めを訴えて株価が下がるリスクもある。金融政策についてはニュートラルとせざるを得ないだろう。為替動向についても、少なくとも日本の政策で動く可能性は低い。
(※情報提供、記事執筆:大和証券 チーフエコノミスト 末廣徹)