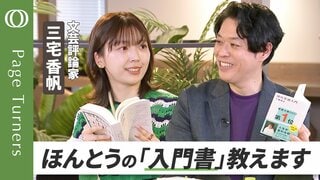警戒される財政拡張
石破首相の政策自由度は、さらに狭まった。当面は秋の経済対策が注目である。補正予算は大規模化するリスクがある。2023年度補正は国費13兆円を上回ることが目途になる。中身は、自民党の選挙公約であった電気ガス代、ガソリン・灯油等の価格支援の延長がある。低所得層への給付金も追加される見通しだ。金融市場の関心は、補正予算の中身がよりばらまき的になるかどうかである。
石破政権にとって、財政運営の自由度は小さい。すでに概算要求が8月に行われて、12月に2025年度予算案がまとめられる。政権の主要政策はこの予算案で実行されるものだから、現時点で独自色のある内容は盛り込みにくい。むしろ、裁量が働くのは、見かけ上の予算規模を膨らませられるかどうかになってしまう。日本の政治には予算規模を膨らませるほど景気刺激的になるという、見た目にこだわる習慣が根強く残っている。もはや給付金などで日本経済が本質的に改善することはないのに、家計向けの減税・給付金がまた繰り返されそうなことは残念でならない。2025年度に何とか見えてきた基礎的財政収支の黒字化(国・地方を併せたPB黒字化)も、前途は危うくなってきた。
今後のスケジュールを確認すると、2025年夏の参院選まで多くのイベントがある。
2024年11月 米大統領選挙
12月 税制改正大綱
2025年度政府予算案
2025年1月 米大統領就任(早い時期の首相訪米)
2~3月 春闘交渉
4月 大阪万博(10月まで)
7月 参議院選挙
こうした日程をみれば、予定がかなり詰まっていて、石破政権には考える余裕が十分には与えられていないことがわかると思う。与党過半数割れになったことで、攻めるよりも守る方で手一杯になって、支持を集めるような政策が打ち出しにくいことが心配されている。
石破政権には、そうした中で、事態を挽回するための独自色のある経済政策を打ち出せるかが焦点である。
活路はどこにあるか?
石破首相が、自民党総裁選挙後に失敗してきたことがあるとすれば、それは独自色を消してしまったことだろう。他人の意見に流されていると思われたことは、マイナスに映った。
だから、今から石破首相が採るべき選択肢は、独自色のある政策になる。石破首相自身はまともな金融・財政政策運営を志向する人物である。大方が「また流されるだろう」とみている逆に動くことがチャンスだ。これは、経済政策ではなくとも、対米外交、防衛政策でも同じだ。「失うものは何もない」と覚悟を決めれば、批判を顧みずに自分の政策を実行できる。今は、財政拡張に走るとみられているから、そうした観測に流されずに、アイデア本位に動く。
具体的に言えば、石破首相にとって色が出せるのは地方創生である。現時点では、予算において交付金を倍増させるという方針があるが、そうした量的なものではなく質的な変化を期待したい。地方創生をやろうとすれば、インバウンド戦略や、リモートワークの拡充・支援、工場誘致など、いくつも手はある。地方自治体もそうした国からの支援を期待している。そうしたところに衆目の関心を移せるかどうかにかかっている。ピンチをチャンスに変えることが活路になるだろう。
(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト 熊野英生)