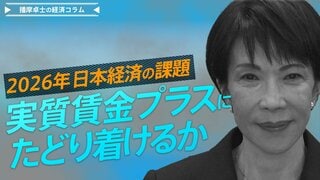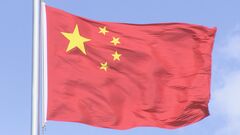(ブルームバーグ):米テクノロジー企業の中心地シリコンバレーは、米政府との関係が大きく変わると覚悟している。バイデン政権の政策の多くを覆すと表明しているトランプ前大統領がホワイトハウスに返り咲くためだ。
人工知能(AI)に関して、トランプ氏は安全規制を設けることを目的としたバイデン大統領の行政命令を破棄すると公言。反トラスト法(独占禁止法)では合併を巡る規制緩和を求めると予想され、半導体については政府支援により国内の半導体生産を促進する超党派のプログラムに懸念を示している。
業界のリーダーたちは、第1次トランプ政権の緊張関係が繰り返される可能性があるとみている。トランプ氏は、アマゾン・ドット・コムの創業者ジェフ・ベゾス氏をはじめとする一部のテクノロジー起業家と衝突する一方、アップルのティム・クック最高経営責任者(CEO)らとは親密な関係を築いた。
トランプ氏は大統領退任後、アルファベット傘下のグーグルが自身に関する良いニュースを抑制していると不満を述べ、メタ・プラットフォームズが2021年に「フェイスブック」と「インスタグラム」から自身を不当に追放したと非難している。

一方、トランプ氏は選挙戦で世界一の大富豪イーロン・マスク氏らテクノロジー業界の一部大物たちから支援を受けていた。マスク氏は、トランプ氏を支持する政治活動特別委員会(スーパーPAC)や共和党の議会選キャンペーンに1億3000万ドル(約200億円)以上の私財を投入。
ペンシルベニア州で行われたトランプ氏の集会で演説したマスク氏は、自身が所有するソーシャルメディア「X」(旧ツイッター)を通じて、共和党のメッセージを数億人のユーザーに発信した。
マスク氏は次期大統領と親しい関係にあるため、テスラやスペースXなど、自身の事業に影響を与える政策に関与できる立場にあり、電気自動車(EV)や宇宙産業の競合他社が契約や監督に関し不利な立場に置かれる可能性もある。
トランプ氏との関係を改善させる方法を見つけた大物もいる。 7月13日の暗殺未遂事件に対する同氏の対応を「最高だ」と称賛したメタのマーク・ザッカーバーグCEOだ。そしてフェイスブックは偽情報対策の多くを取りやめた。
米紙ワシントン・ポストのオーナーであるベゾス氏は、選挙の2週間前に民主党のハリス副大統領を支持する社説の掲載に待ったをかけた。
トランプ氏が大統領としてどれだけの成果を上げられるかは、共和党が下院の主導権を維持できるか次第だ。共和党はすでに上院を民主党から奪還しており、これによりトランプ氏は指名する閣僚ら政権幹部の承認を得やすくなっている。
次期トランプ政権がテクノロジーに何を期待しているのか、詳しく見てみたい。
AI
トランプ氏は、バイデン氏が昨年署名したAI開発者向けに自主的なセキュリティーとプライバシーのガイドラインを定める措置を撤回する意向だ。
この命令は、AI研究へのさらなる資金提供を求め、リスクを軽減する指針の策定において米商務省傘下の国立標準技術研究所(NIST)の役割を拡大し、AIモデルがリリースされる前にテストおよび評価を行う新たな機関を創設するというもの。
具体的な内容には言及していないトランプ氏だが、バイデン氏の政策を「危険」と呼び、イノベーション(技術革新)を妨げると論じている。
トランプ氏は、バイデン氏の政策を「言論の自由に基づくAI開発」に置き換えると述べているが、これは、AIの利用が公平でアルゴリズムに偏見がないことを保証しようとするバイデン氏の取り組みに対する他の共和党員からの批判を反映している。
米戦略国際問題研究所(CSIS)ワドワニAIセンターのディレクター、グレゴリー・アレン氏は「一部の右派政策サークルでは、安全性は検閲と同義語と見なされている」と述べる。
バイデン政権のAI政策の一部は、生き残る可能性がある。その中には、AIインフラのさらなる整備を推進する政策も含まれる。
トランプ陣営は選挙戦でAIの分野で競争力を維持するために米国のエネルギー容量を拡大する必要性を強調しており、その結果、土地や電力使用の許可要件が緩和され得るとアレン氏はみている。
バイデン政権は最近、AIを国家安全保障上の優先事項とし、その基盤となるテクノロジーを中国のような敵対する国の手に渡らないようにすることで米国の主導権を維持するよう政府機関に強く求める覚書を出した。
トランプ氏はこの覚書は維持しようとするかもしれない。また、バイデン氏よりもさらに踏み込んだ輸出規制を通じて行動を起こす可能性もある。
トランプ氏がAI政策の責任者に誰を任命するかは明らかになっていないが、シリコンバレーでの経験を持つバンス次期副大統領が重要な役割を果たす可能性がある。
バンス氏はすでに規制に対し懐疑的な見方を示しており、安全規制について、大手AI企業に業界を支配させる一方で、スタートアップを窒息させるだけだと主張。また、AIモデルにおける左派的なバイアスを防ぐためにオープンソースのテクノロジーを支持している。
反トラスト
第2次トランプ政権は、企業間の提携には寛容になりそうだが、大手テクノロジー企業を標的とする反トラスト法の抵触に対しては積極的に追及し続けると思われる。
トランプ氏はカーン米連邦取引委員会(FTC)委員長に退任を求め、FTCに3人目の共和党支持者を任命することになりそうだ。
また、バイデン氏によって任命された司法省反トラスト局のカンター局長らも退任し、トランプ氏が指名した人物が就任するまで、同省はキャリア職員の手に委ねられることになる。
FTCも司法省も、テクノロジー大手を標的とした訴訟は継続する可能性が高い。アマゾンのように電子商取引事業に対する反トラスト法訴訟に直面している企業は、新たな政権幹部との和解を探る可能性もある。ライブ・ネーション・エンターテインメントやビザなどに対し司法省が起こした訴訟では、変更や決着があり得る。

共和党が多数派となるFTCでも、カーン委員長の優先事項でありながら共和党議員が強く反対していた規則制定の取り組みは後退する公算が大きい。
可能性の低い大胆な動きだが、トランプ氏は気に入らないバイデン政権の案件をすべて取り下げることもできる。
最大の変化は、合併に対するアプローチかもしれない。第1次トランプ政権はビザが計画したフィンテック新興企業プレイドの買収など、一部の注目度の高い取引に異議を唱えたが、概してより友好的なスタンスをとり、多くの場合、条件付きで主な案件を前進させてきた。
クアルコムやシグナ・グループ、ヒューマナなどM&A(企業の合併・買収)を検討している一部の大手企業は、次期政権下でより好意的な姿勢が期待できるとして、選挙後まで案件の最終決定を先延ばしにしている。
TikTok禁止撤回
トランプ氏は、動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」禁止に反対する意向を示している。これは、同アプリを運営する中国のバイトダンス(字節跳動)が所有権を放棄しない限り、TikTokの米事業閉鎖を求める大統領令に署名した第1次トランプ政権からの政策転換だ。
大統領就任前日の来年1月19日までにTikTok売却が行われない場合、TikTokを禁止する連邦法の施行をどのようにして免れるのかは不明だ。
トランプ氏は、21年1月6日に支持者たちが米連邦議会議事堂を襲撃した後、同氏をソーシャルメディアから締め出したとしてメタに対し怒りをあらわにしており、TikTokをメタの有力な競合相手としてみている。
ピュー・リサーチが9月に発表したデータによると、TikTok禁止を支持すると答えた米国人の割合は32%と、23年3月の50%から低下している。
半導体と輸出規制
トランプ氏が大統領選を制したことで、米国の半導体政策には大きな不確実性がもたらされた。
バイデン政権下では、数十億ドルを国内の半導体製造に投じ、貿易および投資制限を活用し、重要な電子部品における中国の取り組みに対抗する政策が実施されてきた。
トランプ氏は最近、インテルや台湾積体電路製造(TSMC)を含む企業からの投資を加速させた画期的な超党派措置である22年のCHIPS・科学法を非難した。
同氏は米国の半導体製造を活性化させるには、外国の半導体メーカーに対する関税の方が、直接的な補助金よりも効果的であると示唆。第2次トランプ政権がCHIPS法を変更しようとしているのではないかという懸念を業界に抱かせている。
対外貿易を巡りトランプ氏は中国からの輸出品に広範に関税を課すとしており、バイデン氏が50%に引き上げた古い世代の半導体に対する関税率をさらに上げるかもしれない。
第1次トランプ政権に端を発するバイデン氏の政策である先進半導体の輸出規制を強化することも考えられるが、外交官や業界ロビイストは、トランプ氏の外交政策の取引的な性質を踏まえ、さまざまな可能性を想定している。
恐らく最大の疑問は、半導体産業の世界的な中心となっている台湾にトランプ氏がどうアプローチするのかということだろう。
同氏は台湾が米国の半導体ビジネスを「盗んだ」と主張し、台湾は自らの安全保障により多くを支払うべきだしている。
先進的な半導体の9割以上を製造している台湾が中国に侵略された場合、世界経済は10兆ドル相当の打撃を受けるとブルームバーグ・エコノミクス(BE)は推計している。
原題:Tech Giants Gird for AI Revamp, Antitrust Pullback in Trump 2.0(抜粋)
--取材協力:Evan Gorelick、Josh Sisco.
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2024 Bloomberg L.P.