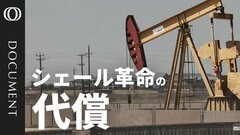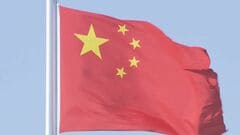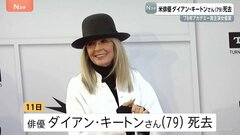(ブルームバーグ):全国の物価の先行指標となる7月の東京都区部の消費者物価指数(生鮮食品を除くコアCPI)は前月から伸びが拡大した。一方、物価の基調をみる上で注目のエネルギーも除いたコアコアCPIは鈍化しており、日本銀行は追加利上げを巡り慎重な判断を迫られそうだ。
総務省の26日の発表によると、コアCPIは前年同月比で2.2%上昇した。市場予想と同じだった。日銀が目標とする2%台を上回るのは2カ月連続。政府による電気・ガス代負担軽減策がいったん終了した影響などでエネルギーが14.5%上昇と前月から伸びが拡大した。一方、コアコアCPIは1.5%上昇と前月の1.8%上昇からプラス幅が縮小し、市場予想(1.7%上昇)を下回った。
インフレの継続や金融政策を巡る要人発言などを背景に、市場では日銀が30、31日に開く金融政策決定会合で、国債買い入れの減額計画と同時に追加利上げに踏み切るとの思惑が急速に広がっている。日銀会合前の最新の物価統計として注目を集めていたが、利上げの判断材料としては決め手に欠ける内容との声も出ている。
第一生命経済研究所の新家義貴シニアエグゼクティブエコノミストは、「今回の重要な点はコアコアが減速したこと」と指摘。結果は「失望させるものではないが、物価の基調に自信を深め、利上げを後押しする材料でもない」と述べた。その上で、利上げを巡って7月会合では「両方の可能性がある」としながらも、自身であれば消費や物価の基調を見極めるため今回は待つだろうと語った。

賃金動向を反映しやすいサービス価格は0.5%上昇と前月(0.9%上昇)からプラス幅が縮小した。総務省によると、サービス価格の伸びの鈍化は宿泊料(10.3%上昇)や通信料(0.6%上昇)が影響した。今年の春闘で平均賃上げ率が33年ぶりに5%を超える中、賃上げコストを価格に転嫁する動きの広がりが注目されている。
野村証券の岡崎康平シニアエコノミストは、「全体としてインフレが沈静化する中で、サービス価格の加速がなかなか明確には見えていない状態」と説明。一般的には賃金統計がしっかり伸びたという評価だが、「春闘の伸び方に対しもう少し伸びて欲しかったというのが正直なところで、好循環が明確に見えたというには迫力不足」と述べ、追加利上げは10月との見通しを示した。
5月の毎月勤労統計調査(速報)では、基本給に当たる所定内給与は2.5%増と1993年1月以来の高い伸びだった。エコノミストが賃金の基調を把握する上で注目するサンプル替えの影響を受けない共通事業所ベースの所定内給与は2.7%増で、同ベースでの公表が開始された2016年以降で最高となった。
基本給31年ぶりの高い伸び、春闘反映-実質賃金は26カ月連続マイナス
ブルームバーグの最新のエコノミスト調査では、国債買い入れの減額計画を決定する7月会合で日銀が利上げを同時決定する切迫した必要性はないとの見方があるなど、同会合での利上げ予想は3割程度にとどまった。一方、9月会合は27%に増加しており、予想を前倒しする動きが見られた。最多は10月会合の35%で、6月会合後の前回調査からは低下した。
総務省の説明
- コアCPIの押し上げ要因は、政府による電気・ガス激変緩和対策事業の終了で、エネルギーの前年比上昇幅が前月から拡大したため
- 生鮮食品を除く食料(2.6%上昇と前月から鈍化)は主にプリンや食パンなどがマイナス寄与。昨年に値上げが行われた影響が一巡したため
- 宿泊料は、全国旅行支援の関係で昨年同期に値上がり幅が大きくなったのに比べて今年は小さかった
- 通信料は、昨年7月に一部の携帯電話会社が料金プランの改定で値上げした影響が一巡した
(チャートとエコノミストコメントを追加して更新しました)
--取材協力:氏兼敬子、藤岡徹.
もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2024 Bloomberg L.P.