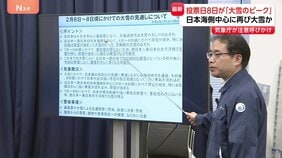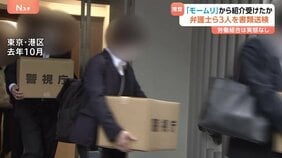1つ目の説:故意に沈められた
湖の中に祭祀を行う場所があり、そこに供えられた供物を入れた器として沈められた。

2つ目の説:積み残しの荷物
湖で船を使って荷物を輸送した際、船着場に積み残した器類が沈んだ

3つ目の説:集落が水没
現在湖底となっている一部は当時、地上にあり、そこに形成されていた集落が沈んだ。

1つ目、2つ目の説について杉本学芸員は、説明がつかないことがあると言います。
土器の発見範囲は湖の東岸ですが、それを図にしたものがあります。

それによりますと、その範囲は南北に約600mにわたって点在しています。土器の発見場所が仮に祭祀場や船着場だとしたら、もっと限定的な範囲に留まるはずで、この2つは考えにくいといいます。
でも、集落が水没するなど、あり得るのでしょうか?あるとすれば、その原因とは?