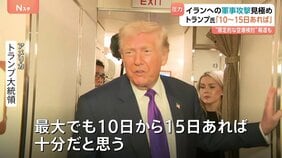その1番の要因として考えられているのが864年にあった富士山の「貞観の大噴火」です。

当時、富士山の麓にあった湖に「貞観の大噴火」の溶岩が流れ込んだ影響で本栖湖の水位が上がり、過去に人が住んでいた岸部の地域が土器ごと水の中へと沈んだのではないか…と考えられるというのです。
佐々木准教授:
「今後、貞観の大噴火の溶岩を詳しく調べることで、昔の湖岸がどの位置にあったのか、水深が昔とどれほど変わっているのかが分かってくるかもしれない」

佐々木准教授ら研究チームは今年2025年も範囲を広げて突き棒調査を行っていく予定です。
突き棒調査の後は次の段階として2026年あたりには湖底のボーリング調査を行い、土器が沈んだ時期を調べていきたいとしています。