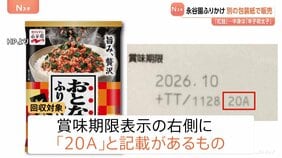田んぼの再生とともに見えてきたものとは?
秋の風物詩・稲刈り。
先週金曜日、山形県鶴岡市の中山地区で、山形大学農学部の学生たちが稲刈りを行いました。

実はこの田んぼ、担い手不足のため作付けが行われなくなった「耕作放棄地」。
学生たちのチームでは、農家の高齢化が進む中で持続可能な農業を目指そうと、肥料や農薬を使わない米作りを研究しています。そのカギが・・・。
山形大学農学部
佐藤 智 准教授
「こんなにタニシがよく効くとは思っていなかったです。大成功です」


人と自然の関わりを研究する山形大学農学部の佐藤智准教授です。
佐藤准教授が選んだのが、この「マルタニシ」。県の準絶滅危惧種にも指定されている貴重なタニシです。
田んぼから100メートルほど離れた水路で見つけたマルタニシを、去年、田んぼに移したところ、コメの育ちが良くなったそうです。
佐藤准教授によりますと、マルタニシには土の中の生態系を変化させて、土壌を良くする効果があるということです。
もう1か所、再生を目指す田んぼに案内してもらいました。
雑木林を歩くこと10分。

到着したのは、なんと、50年も放置されてきた田んぼです。
そこで目にしたのは…。

佐藤准教授
「あーって思いますね」
農家
「2、3日でやられたから」


収穫前の稲は、無残にも踏み荒らされていました。
泥や沼地を好むイノシシの仕業です。
水路を復活させて田んぼにしたことでイノシシが集まるようになってしまいました。
収穫量は、想定の3分の1のおよそ30キロ。
それでも佐藤准教授は、こうしたトラブルにも地域を知るためのヒントが隠されていると話します。
山形大学農学部
佐藤 智 准教授
「あんなに生物が多様な自然環境ってなかなかないので、そこで、かつてはあった田んぼが消えて復元するっていうのは研究者としてひとつのロマン」
研究チームでは、今年得た経験を生かして、来年以降も自然を生かした米作りを続けていくということです。