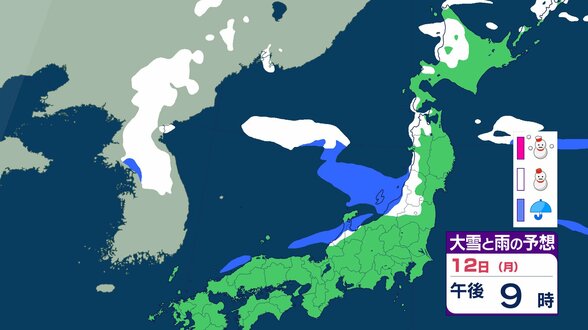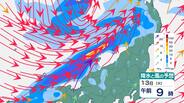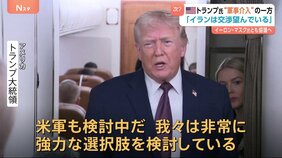“AYA世代” と呼ばれる若いがん患者が自分らしく過ごすためにどのような方策があるのかを考える市民公開講座が2日、富山市で開かれました。
市民公開講座は、富山大学附属病院総合がんセンターと富山県産科婦人科学会の共催で開かれました。

AYA世代は、日本国内では15歳から39歳までとされていて、この世代が新たにがんと診断されるのは年間約2万1000人です。がん患者94万人全体のうち2.2パーセントと割合が小さいため、まわりに悩みをわかってもらえる人が少なく孤独になりやすいといわれています。
また、進学や就職、仕事や会社、恋愛や結婚、出産や子育てなどさまざまなライフイベントに直面するため、その分の経済的、精神的負担が大きいという課題があります。
市民講座では、がん治療の経験をふまえAYA世代の患者会を運営している看護師や、がん対策の広報や患者同士をつなぐ活動を続ける団体の代表などが、当事者としての経験談を語りました。

このなかでは、一般的にAYA世代はSNSなどを通じての情報収集には慣れているが、ネット上の情報には間違いがあったりビジネスとして患者を呼び込む広告的な要素も多かったりするなどの問題もあり、情報を正確に読み取る大切さが重要だと指摘が出ていました。
そのうえで、同じ立場の仲間が集う患者会などを通じ、信頼できる情報を交換したり、悩みを共有して不安が和らいだりすることもあるとの意見が出ていました。

治療や今後の生活については、将来への見通しがつかないつらさや、治療により子どもを授かる能力にどう影響するかなど、今後の人生にかかわる様々な問題、支援策についてさらに情報が必要との意見が出ていました。
がんと診断された直後は、治療への不安から冷静に判断することが難しくなる患者も多いことから、市民講座では医療分野以外でのサポート体制や、相談できるネットワークの重要性が強調されていました。
患者会などの情報は、富山県内の各がん拠点病院で予約なしに利用できる相談支援センターを活用したり、富山県のがん総合相談支援センターを利用するなどして正確な情報に接することができるということです。