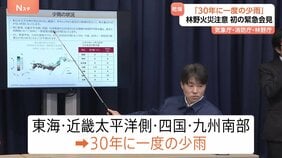鈴木正則会長:
「いろんなイベントをする中で住民相互の絆や親睦をつくって、いざ何かあった時にはお互いが助け合って逃げられるようなことをしようという意識は非常に強いと思います」
こうした住民の活動を、災害の記録として今後の防災に役立ててもらおうという取り組みも行われています。
信州大学の防災教育研究センターによる、災害記録のデジタルアーカイブ化です。
常和地区を含め、台風19号で被害を受けた県内各地の住民の体験談や、被害状況の写真などを1つのサイトにまとめて公開。
6日から長野市役所でパネル展示も行われています。
信州大学の廣内大助(ひろうちだいすけ)教授は、住民の活動を記録していくことは、今後の防災に大きく生かせると話します。
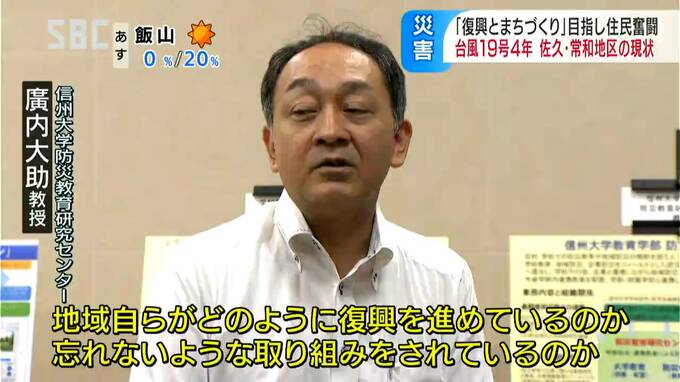
信州大学 廣内大助教授:
「地域自らがどのように復興を進めているのか。忘れないような取り組みをされているのかをしっかり伝えたいなと」
「この地域で財産として継続していけるか。こんな風にうまく復興できたということをうまく伝えていく大事な時期だと思っています」
常和地区で現在抱えている問題が、なかなか進まない復旧工事です。
鈴木正則会長:
「この辺なんてそのままですよ。ガードレールも浮いたままだし」
「丸4年たってもこんな感じですよ」

地区内を流れる田子川では、川底を広げ、護岸をコンクリートで囲う大規模な改良復旧工事が続いていて、川を渡る橋は一つしか使えません。
工事を行う県は、今年度中の完了を目指していますが、人手不足や、部材の高騰などから遅れが出ているといいます。

鈴木正則会長:
「早く終わってほしいというのが本心で、早く終わらないと水が出た時に大変な思いになるという、皆さん身をもって体験しているので一日でも早く工事が終わることを願っています」