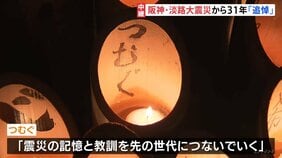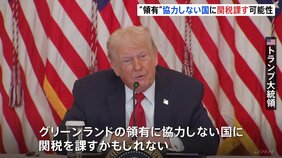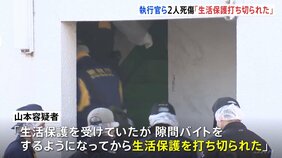小さなキャンバスに描かれる雅な平安時代の風景。

長野市出身で、90歳を過ぎた今も現役で活躍する絵付け作家の展覧会が話題となっています。

平安時代の貴族たちが桜の木の下で花見を楽しむ一幕。
10センチほどのハマグリの貝殻に描いてあります。
「貝合わせ」と呼ばれ、平安時代に貴族階級の遊びとして始まって以降、江戸時代には芸術性が高まり、嫁入り道具として用いられてきました。

絵付けをしているのは、90歳を迎えた長野市松代町出身の生越仁子(おごしきみこ)さん。
50歳の時、都内で営んでいた懐石料理店で廃棄されるハマグリを活用したいと独学で始めました。

貝合わせの魅力は、2枚で1つの絵を完成させるデザイン性だと言います。
(生越仁子さん)
「楽しい、楽しい、それだけ。細ければ細いほど楽しい。1ミリの3分の1ぐらいの線をいつも平気でひきます」
これまでに制作した作品は、実に4600点以上。
その一部が並ぶ作品展が、25日から故郷の松代町で始まりました。

源氏物語の一幕を描いたものや、平安時代の女性貴族の表情をとらえたものなど、100点ほどが並んでいます。

(訪れた人は…「素晴らしいの一言です」「写真とはまた違って現物を見られるなんて夢のようです」

手持ちの貝殻が尽きるまで毎日創作を続けると語る生越さん。
作品展は5月1日まで松代町の寺町商家で開かれています。