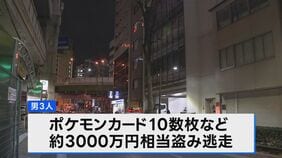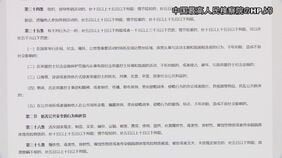領土を決めた協定から80年後に揃った3国のトップ
そんな現状の中で、トランプ政権が再び登場した。つまり、「領土」をキーワードにすると、自国の領土を広げた、また、広げようとしているリーダーが、ロシア、中国、アメリカという、極めて大きな影響力を持つ大国に揃ったわけだ。
そのトランプ大統領は、習近平主席、それにプーチン大統領とも「自分なら、話ができる」と言っている。
トランプ氏が好んで使うフレーズは「ディール」(=取り引き)だ。法外な要求を持ち出して、交渉し、落としどころを迫る、と思うのが一般的だが、だれもが「あり得ない」と思うことだって、取り引きの材料にされかねない。私は、どうしても第二次世界大戦後の世界地図を決めたといわれる会談を連想してしまう。
それは、日本の敗戦の半年前、1945年2月、当時のソビエト連邦のヤルタ近郊で開催された、ヤルタ会談だ。イギリスのチャーチル首相、アメリカのルーズベルト大統領、それにソ連のスターリン書記長の連合国3首脳が会した。
そこで結んだヤルタ協定によって、ドイツの分割統治、バルト三国の帰属などヨーロッパの戦後処理が決まった。アメリカとソ連は、これとは別に秘密協定を締結し、北方領土、朝鮮半島な台湾など日本の領土の取り扱いも決まった。今日の北方領土問題の始まりと言ってよい。
80年前、3人の首脳が大戦後の領土を決めた。そして80年後の今日、領土への野心をあらわにする3人が揃った。領土のために「取り引き」が行われかねないわけだ。
習近平主席が、自国の領土として執着するのが、台湾だ。中国は「台湾問題は中国の核心的利益の核心だ」と位置付けている。トランプ政権誕生によって、台湾では「台湾が大国のディールの材料になるかもしれない」という論調が出ている。アメリカがグリーンランドを得る=「力による現状変更」をしたら、中国が台湾に侵攻しても、アメリカは文句を言う資格がなくなる。
ヤルタ会談から80年、戦後80年ということで、今年は国連の創設から80周年でもある。パレスチナ問題、ウクライナ問題など、国連の機能低下・機能不全が指摘されている。
アメリカ、中国、ロシアは国連の常任理事国。その3カ国の首脳が、周囲に忠誠心を求め、独裁色を強めている。そして、5つの常任理事国の残り2つ、イギリス、フランスは政権が不安定で、内向きになりがちだ。2つの世界大戦を反省した20世紀が終わり、平和を希求していくべきはずの21世紀に、国際的な秩序を維持できない状態だ。
就任演説で語った「不可能を可能にする」とは?
最後に、トランプ大統領の就任演説に戻ろう。トランプ氏は昨年7月、遊説中に銃撃された。命が救われたこと。そして、大統領に返り咲いたことを並べ、こう語っていた。
「私はアメリカを再び偉大にするために神に救われた。だからこそ、愛国者による政権の下、尊厳と権力、強さをもってあらゆる危機に対処するために日々努めていく」
「アメリカでは不可能なことなど何もないこと――。私は今、それを証明するためにここに立っている。アメリカは不可能を可能にするのが最も得意だ」
「不可能を可能にすることが最も得意」。それには世界地図の塗り替えも含まれているのだろうか。
◎飯田和郎(いいだ・かずお)

1960年生まれ。毎日新聞社で記者生活をスタートし佐賀、福岡両県での勤務を経て外信部へ。北京に計2回7年間、台北に3年間、特派員として駐在した。RKB毎日放送移籍後は報道局長、解説委員長などを歴任した。