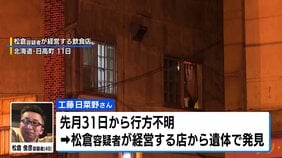周辺国との関係改善の背景に“経済不振”
中国への好ましくないイメージは、日本に限らない。習近平主席は先週、インドのモディ首相と会談した。インドも日本と同じで、中国の隣国だ。国境問題を抱えるインドとの首脳会談は実に5年ぶりだった。
中国の国内経済が不振を極める。中国が、周辺環境を再構築しようという意欲を持っている背景には、やはり中国経済が難しい状況に陥っている影響は大きい。だからニシキゴイを含め、日本産水産物の輸入を認め、「経済」に関して、日本と協力していきたいという意向が強いのだろう。
中国経済の苦境は、さまざまな数字からも見て取れる。中国が目標に掲げた今年の経済成長率は「5%前後」。先週18日に発表された今年第3四半期(7~9月)の経済成長率は、前の年の同じ時期に比べて4.6%の伸び。その前の3か月=4~6月の4.7%増からさらに減速した。1~9月期で見ると、4.8%だった。年間目標の「5%成長」(*昨年通年5.2%)の達成は微妙だ。
今年も残り2か月。「来年は景気のさらなる落ち込む」と指摘する観測が早くも出ている。最大の課題は不動産不況だ。不動産取引に依存してきた地方財政の悪化へと波及している。先月末には共産党の重要会議である政治局会議が開かれた。会議の内容が発表されたが、現在の経済情勢について、取るべき姿勢を、こう総括している。
「困難を正視し、責任感と緊迫感を強めなければいけない」
「困難を正視する」。政治局会議では過去、経済の論議はあまり例がない。危機感の表れといえるだろう。国内経済に対し、中国政府は、金融緩和策をはじめ、次々と景気刺激策を打ち出している。
関係改善は「自分たちの論理の枠内で」
一方で、中国当局は、日本人児童刺殺事件の詳細を明らかにしていない。スパイの罪で起訴された日本製薬会社社員についても、説明がないままで、日本の世論をいらだたせている。
日本との関係改善は、あくまで「自分たちの論理の枠内で」ということかもしれない。石破茂総理が就任した時に、習近平主席は祝電を送っている。3年前、岸田文雄総理が就任した時と、祝電の文言が微妙に異なる。岸田氏の時にはなかったこんな一節が、石破氏への祝電にはあった。
「日本が中国と向き合って進み、両国の戦略的互恵関係を包括的に推進し、建設的で安定した中日関係の構築に力を注ぐことを願う」
「日本が中国と向き合って進み」…の部分。日中両国が共に向き合い、ではない。読みようによっては「こっちを向いて」、さらには「日本は米国ばかり向くな」という、やや高圧的な意味合いにも受け止めることもできる。岸田総理への祝電にはなかった。日米を中心にした安全保障の強化に意欲的な石破総理に向けたけん制にも思える。
中国は「自分たちが、真の強国になる道のりには、米国が立ちふさがる」と考える。だから、ロシアや北朝鮮も含めて、国際社会で仲間づくりを進めている。米国と同盟関係にある日本とは、米国を視野に入れながら、また、現在の国内経済を考えた関係を構築しないといけないわけだ。
昨日の総選挙で、与党が議席を減らした。足元が揺らぐ石破政権は、外交や安保で得点を稼ごうとするかもしれない。石破総理が熱心な安全保障の主な対象は、やはり中国だ。日本の政権の弱体化は、中国にとっても歓迎できない事態と言えるだろう。
◎飯田和郎(いいだ・かずお)

1960年生まれ。毎日新聞社で記者生活をスタートし佐賀、福岡両県での勤務を経て外信部へ。北京に計2回7年間、台北に3年間、特派員として駐在した。RKB毎日放送移籍後は報道局長、解説委員長などを歴任した。