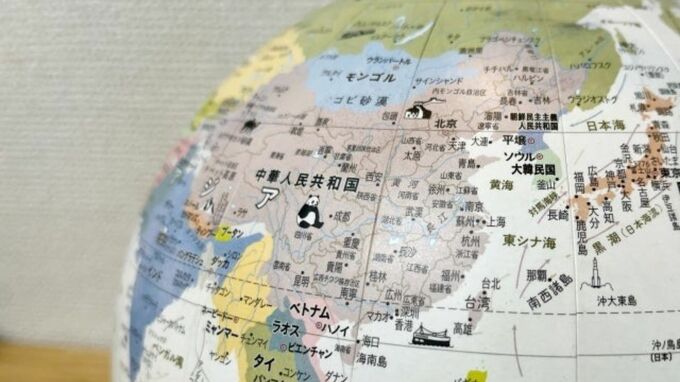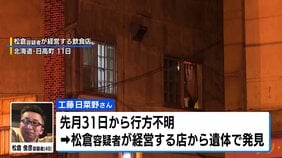中国が先日、台湾近海で軍事演習を行った。台湾をぐるっと取り囲むような大規模な演習だった。東アジア情勢に詳しい、飯田和郎・元RKB解説委員長が10月21日に出演したRKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』で、台湾の頼清徳総統が行った中台関係に関する演説、そしてそれに反発した中国の軍事演習を分析した。
頼清徳総統の演説に中国側は猛反発
1週間前の10月14日「中国人民解放軍が台湾近海で演習を開始した」という発表が飛び込んで来た。注目したいのは、演習のきっかけと思われるものだ。
まずは、どんな演習だったのかを紹介しよう。中国人民解放軍で、台湾方面を管轄するのが東部戦区。その東部戦区が14日早朝から、陸・海・空軍、それにロケット軍などが加わり演習を行った。空母「遼寧」も参加した。
演習を行った区域は台湾の北部の台北、南部の高雄など台湾の主要な港湾をもつ6つの沿岸都市の沖合だった。中国軍は演習の目的として、「重要な港の封鎖、そして制圧」することを挙げていた。つまり、「中国軍は、ことが起きれば、台湾で物資や人員の移動を遮断できる。経済の流れを止められる」――その能力を示すことが狙いだった。私が今回の演習で、見出せる2つの意義のうちの1つが、港湾封鎖という、演習の具体的テーマだ。
中国の軍隊が、台湾を包囲する形で行う大規模な演習は、台湾の頼清徳総統が就任した直後の5月以来。今回の演習は、台湾の建国記念日にあたる「双十節」=10月10日の4日後だった。2つ目の注目点は、その双十節で、頼清徳総統が行った演説内容に、大きく関係していることだ。頼清徳総統は、中国との関係について、こう述べた。
「中国は台湾を代表する権利がない」
「中華民国は、中華人民共和国に隷属しない」
特に2番目の「中華民国(台湾の正式名称)は、中華人民共和国に隷属しない」。この発言が2つ目のポイントであり、中国側は猛反発したわけだ。台湾の建国記念日に相当する日の演説で、そう言った。もう一度、紹介しよう。「中華民国は、中華人民共和国に隷属しない」。この頼清徳総統の発言を、中国メディアは、このように位置付けた。
「頼清徳の演説は、独味と毒味に満ちている」
どくみ…。音は同じだが、字体は違う。1つ目の「どくみ」は「独立の味、つまり台湾独立の意味」、2つ目の「どくみ」は、「毒々しい味、即ち、悪意のある、危険な意図という意味」。独立の「独」と毒々しいの「毒」は、中国語でも同じ発音。頼清徳総統による「中華民国は、中華人民共和国に隷属しない」の演説は、中国側からすれば「台湾独立を目指し、悪意に満ちた、許すことのできない内容だ」と猛烈に非難しているのだ。
『二国論』が25年の月日を経てよみがえった
中国のメディアは、この演説全体に、このように怒りを表している。
「これは、新たな『二国論』である」
「新たな『二国論』」と糾弾しているが、そもそもの二国論とは、今から25年前の1999年7月、当時、台湾の総統だった李登輝氏がドイツの放送局とのインタビューで、打ち出した。中台関係についての考え方だ。
「台湾海峡両岸の関係を位置づけると、少なくとも『特殊な国と国の関係』である。一つの合法政府と一つの反乱団体、あるいは一つの中央政府と一つの地方政府というような『一つの中国』の内部の関係ではない」
中国と台湾の関係は「特殊な国と国との関係」。これが李登輝氏の二国論だ。歴史的経緯から「特殊な」という枕詞がつくが、要は「中国と台湾はすでに別の国だ」というもの。当然ながら「台湾は自分たちの国の一部」という原則を絶対に曲げない、中国共産党政権の猛反発を招いた。
中台関係は「特殊な国と国との関係」、李登輝氏が25年前に語った二国論があって、今回の頼清徳総統の演説内容こそが「新たな二国論」。中国側はそう決めつけたわけだ。中国からすれば、「あの憎々しい李登輝の、あの憎々しい『二国論』が25年の月日を経てよみがえった」…。そういう認識だろう。