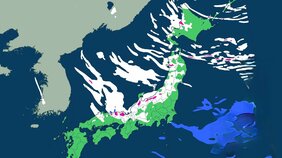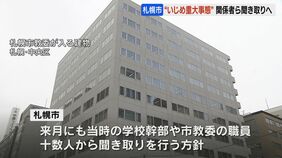3年前に妻を亡くし…「御手洗を死なすな」
実は、局長が御手洗さんを「死なすな」と言ったのには、事件とは別の事情もありました。御手洗さんはこの3年前、奥さんも病気で亡くし、憔悴しきった御手洗さんを支えたのが子どもたちだったからです。
それは父親としての責任感もそうですが、むしろ本当に子どもたちがお父さんを励まし元気づけ、御手洗さんが「どっちが大人か分らんな」と苦笑いするほどでした。末っ子の一人娘だったさっちゃんまで育て上げることが、当時の御手洗さんのただ一つの人生の目標で、きっと奥さんにも誓ったはずだからです。
佐世保に向かう車中から御手洗さんに連絡し、家とは離れた、とある施設で落ち合いました。佐世保支局は小さなビルで、2階が支局、3階が支局長住宅という造り。しかも隣は、各社の取材拠点となっている佐世保警察署ですから、自宅に帰れば混乱が続くのは必至で、二男(さっちゃんのお兄ちゃん)や支局まで巻き込んでしまう。
父親として、支局長として、それは避けたいという思いと、帰ってくるさっちゃんをせめて静かに休ませてあげたいという思い――御手洗さんの意向を確認して、長崎県内の別の市にあった奥さんの実家に、御手洗さんと二男は当面、移ってもらうことにしました。
御手洗さんの同期入社で親しい高原克之さんも合流して、警察など外部対応は2人が窓口になると決め、県警にもその旨と居所を伝え、司法解剖を終えたさっちゃんのご遺体は、私が引き取りに行きました。さっちゃんが帰ったのは深夜でした。
役割は「遺族のケア」取材・報道とは一線を引く
ここでいくつか触れておかなければならないことがあります。一つは、取材と遺族のケアと、毎日新聞は厳密に二つの役割を分けたということです。今お話しした通り、私は遺体を引き取ってさまざまな説明を受けましたが、そのことも含めて同僚記者に一切、遺族の代理として聞いたことは話しませんでした。
この事件報道が終わるまでずっと。御手洗さんも、高原さんも。きれいごとに聞こえるかもしれませんが、それはメディアとしてフェアではないという考えを、会社も御手洗さんも共有していました。おかげで、私と高原さんは御手洗さんらのケアと、さまざまな手続きの代行に専念できました。
犯罪被害者支援や「手記代読」のテストケースにも
もう一つは長崎県警の対応です。県警はこの5年前に「被害者対策推進要綱」を制定して被害者や遺族の支援に取り組みはじめ、ちょうどこの年の8月に「犯罪被害者支援室」を立ち上げる直前でした。これはのちに県警幹部に聞くのですが、まさにそのテストケースとなったそうで、遺族が何を望み、警察に何ができるのか、親身に相談に乗ってもらえました。また「この経験が、その後の被害者ケアに役立った」と言われたことが、かすかな光になったのを覚えています。
最後の一つは、取材する側だった私たちが、初めて被害者の立場になったということです。実は事件当日、御手洗さんがどうしても聞き入れてくれなかったことが、一つだけありました。記者会見です。「今は無理です」と必死に止めましたが、御手洗さんは「自分も取材をしてきた人間。被害者側になったからといって、逃げるわけにはいかない」と、聞きませんでした。そう話せば、記者の私たちが言い返せないと思ったのでしょう。
ただ今月1日のインタビュー記事で、御手洗さんは「(当時中学生と大学生だった)2人の息子に取材が及ぶのを避けたかった」と語っていて、こちらの思いが強かったでしょう。また、加害少女の供述などが明らかになった後、再度の会見要請はさすがに精神的に厳しいという医師の助言も受けて弁護士が止め、手記を書いて弁護士が代読しました。このやり方はその後、さまざまな事件で今も踏襲されています。
また、どうやって調べたのか、さっちゃんの葬儀の日、ある雑誌記者が奥さんの実家を張り込み、写真を撮られました。その後は急増です。事件以降、泣き通しだったおばあちゃんにも辛く、ご近所にも迷惑が及ぶため、ひっそりと佐世保に戻りました。御手洗さんの元には多くの手紙が届き、私たちが読んで差支えのないものだけ渡しました。中には新興宗教の誘いや中傷に近いものもあったからです。当時はまだSNSが普及する前でしたが、今ならこの比ではないでしょう。そんな被害者側の思いを、身をもって知った日々でした。