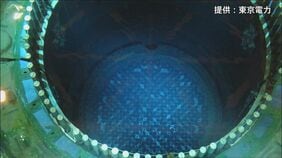エディエさんの脳裏には、キーウの街でロシアによる攻撃から家族で避難したときの光景が鮮明に焼きついています。昼夜問わず鳴る空襲警報。そのたびに3人で地下鉄の駅などに駆け込み、しばらく経ってから家に戻る日々を送っていると、ある日、ファジリャさんが精神的な疲れから「もうどこにも行かない」と言いました。
エディエさん
「生き残れば、おばあちゃんと幸せに過ごすことができます。もし、死ぬことになったら3か月前に亡くなった大好きなおじいさんと会えます。だから、もうこれ以上、避難場所には行かないと決断しました」

「2人を守るために母としてどう動くべきか」―。エディエさんは毎日のように決断が続きました。
ある日、ファジリャさんが自宅で転倒し、足に大けがをします。「万が一のとき、娘を背負って逃げることはできない…」。そのとき、ちょうど連絡をくれた広島の友人を頼って、姉妹を日本に避難させることを決めました。

エディエさん
「ファジリャは戦争が始まってから毎日、『私の将来はどうなるの? お母さん、どう思う?』といろんな言い方で同じことを聞き続けていました」
広島で過ごす間、19歳と20歳の2人にとっては将来が描けないことがなにより不安なことでした。
エディエさん
「2人はキーウに戻っても電気やガス、お湯がないかもしれないことは全く怖がっていません。それよりも自分の将来のことを特に不安に思っていました」