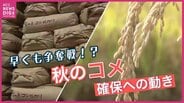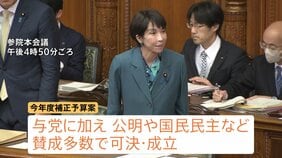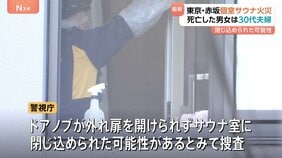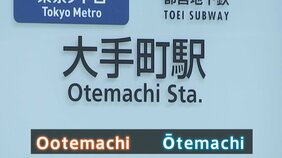10年ひきこもり、家族の支えで踏み出せた 結婚も あきらめないで
社会とつながらず、長期にわたって家庭にこもる「ひきこもり」。国は、全国に146万人いると推計しています。人間関係や就職・受験などきっかけはさまざま。最近は、80代の親が50代のひきこもりの子どもの生活を支える「8050問題」も深刻です。
青少年ワークサポートセンター広島 杉野治彦 代表理事
「(ひきこもりが)長期化していくと、ご本人の体調や状態もどんどん悪くなり、悪循環に陥ってしまって、気づいたら20年・30年たったという人もいる」

自宅から出られない人には、訪問支援もしています。
青少年ワークサポートセンター広島 杉野治彦 代表理事
「今からですね、訪問にいく彼のところに差し入れです。ふだん、テレビばっかり見てらっしゃるので」
訪ねたのは30年間、ひきこもりを続ける50代の息子と、80代の父親。テレビ取材はできませんでしたが、杉野さんはこうした「8050世帯」は孤立する場合が多く、親が支えられなくなって初めて明らかになるケースが増えているといいます。
青少年ワークサポートセンター広島 杉野治彦 代表理事
「ご両親が高齢に伴って介護が必要になってきて、介護スタッフが自宅でいろんなサービスするにあたって、いや実は息子さんがいらっしゃったんです、ひきこもっていらっしゃったというケースが最近、増えています」
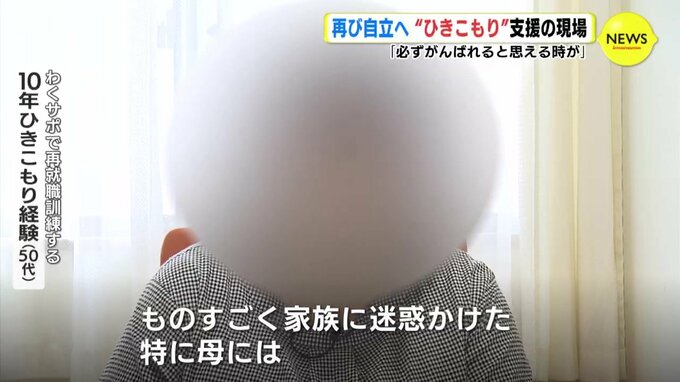
30代から10年近くひきこもったこの女性は、家族の支えで踏み出せたといいます。
10年ひきこもり経験(50代)
「(母の勧めで)スポーツクラブに通うようになって、生活費稼いで自立しないといけないなと思い始めたんですよね。ちょっとおしゃれもしてみたいなと。ものすごく家族には迷惑かけたなと思って。特に母には。家族の支えがあったからこそだなと今も思う」
母親とともに「わくサポ」を訪れ、今は再就職に向けた訓練を続けています。ここで出会った、同じく10年間ひきこもっていたという男性と結婚もしました。
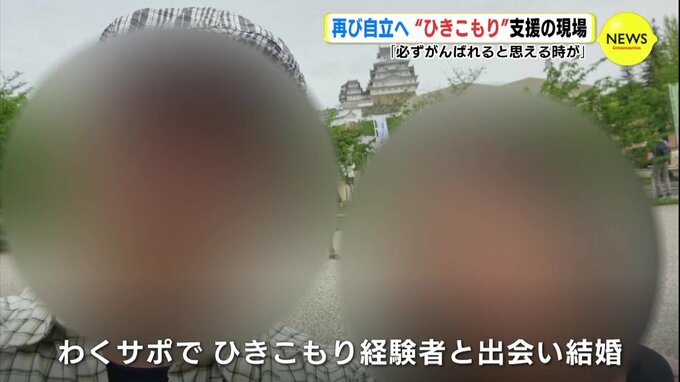
杉野さんは、ひきこもりの人たちを理解してもらおうと月に1度、トークイベントを開いています。これまで1000人あまりの相談を受けてきた経験から、あきらめなければ、その人なりの解決策は必ず見つかると訴えます。
青少年ワークサポートセンター広島 杉野治彦 代表理事
「(ひきこもりの人は)本当はもっと違う形で、世の中でがんばりたいはずなのに、そのやり方が分からないだけなんだなって。そういうふうにちょっと思えるだけでも、その子に対する声のかけ方だったり、かける言葉の中身は絶対に変わってくるはずなんですよ。もしかしたら、ぼくもわたしもがんばれるかもしれんというタイミングが、それを続けていたら必ず来るんですよ」
社会から気づかれず、家の中だけで生活するひきこもりの人たち。本人とその家族は外部からの支援を必要としています。
※「わくサポ広島トークイベント」は7月17日(月・祝)午後1時半から、広島市南区の広島市総合福祉センターで開かれます。無料で個別相談も行うということです。