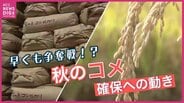およそ3万3600人―。社会とつながらずに自宅にこもる広島県内のひきこもりの推計値です。ひきこもりの状態が長引き、若い世代だけでなく、中高年や女性のひきこもりも増えているといわれます。こうした人たちが、再び自立して生活できるよう支援する男性を取材しました。
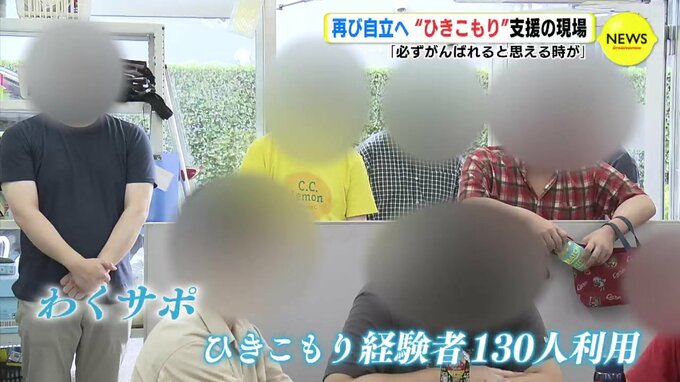
杉野治彦 さん。ひきこもりの人たちを支援する「青少年ワークサポートセンター広島」の代表です。
広島市内や廿日市市に施設を持つ通称「わくサポ」。ひきこもりを経験した10代から60代までのおよそ130人が利用しています。
青少年ワークサポートセンター広島 杉野治彦 代表理事
「(ひきこもるのは)人と接していくことに対する不安や、恐怖に近い思いがあって、自分ひとりの力では踏み出せずに、結果的に家の中にとどまってしまっている」
広島大学 教育学部で障害児教育を学んだ杉野さん。「わくサポ」を立ち上げたのは11年前です。

スタッフは、社会福祉士や臨床心理士などおよそ50人。再び、社会とつながり、自立できるよう、料理や運動などの「生活訓練」から始め、最終的には就職を目指して、作業や職場実習などの「就労支援」を行います。
今はわくサポが経営するパンの専門店で働く30代の男性。高校に進学してまもなく不登校になり、そのまま15年間、ひきこもりました。

15年ひきこもり経験(30代)
「自分の場合、何かきっかけがあったということではなくて、まあ学校、雰囲気ですかね、そういうのがちょっとなじめなくて」
― いじめは?
「そういうのはないです。自分で動き出すタイプ、自発的に何か行動するというのがなくて、受け身でいたら、なんかずるずる15年。そういう感じですかね」
家族以外と会話をせず、買い物や散髪にも行かず。自宅でネットやテレビを見て過ごしました。母親が「わくサポ」に相談したことで杉野さんとつながりました。
15年ひきこもり経験(30代)
「自分なんかは、外部との関わりが全くなかったので、15年という長い期間、ひきこもることになったと思う。(今、ひきこもっている人は)何かしら外とのつながり、自分からというのは難しいと思うけど、何かしら見つけてほしいなとは思いますね」