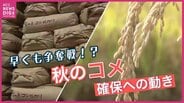広島県三原市に伝わる県無形民俗文化財「御調八幡宮の花おどり」が9年ぶりに復活しました。伝統文化の継承に向けた町内会などの取り組みを取材しました。

三原市八幡町の御調八幡宮に鉦(かね)や太鼓の音が響きます。この踊りを総じて、「花おどり」と呼びます。江戸時代から御調八幡宮に奉納していたとされ、もとは「雨乞い踊り」だったといいます。
高齢化や世帯数の減少などで人が集まりにくいこともあり、毎年の開催はできていませんでした。今回は2015年以来となる、9年ぶりの開催です。
「花おどり」を復活させ町内会を盛り上げようという声を受け、八幡町内会長の 藤田善久 さんが中心となって地域に声をかけていったのです。町内会長就任1年目だった2023年5月に実施する方向でまとまりました。
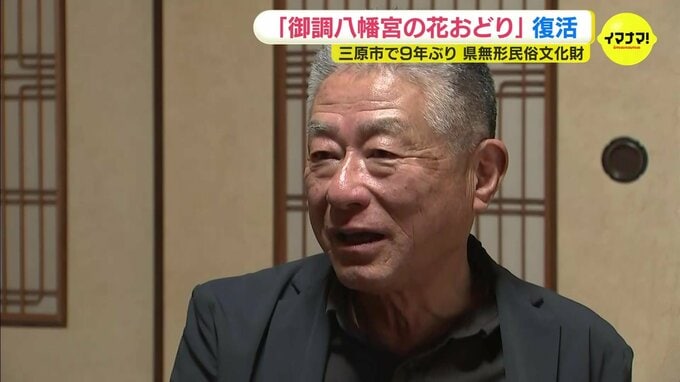
藤田善久 さん
「後世に残していかなきゃいけない踊り。特にそこを考えております。われわれの代だけじゃなくて、20年~30年先、もっと先までこの踊りを残したい」
本番を1週間後に控えた4月6日、地元の公会堂で踊りの練習が行われました。日が暮れ、続々と住民たちが集まってきました。今回は総勢70人で踊ります。5種類の踊りを通しで行う練習が始まります。

大人と大人の間には子どもたちの姿も…。小学生を中心に16人が踊りに参加しています。踊りの練習はことし2月から。月に3回程度、練習をしてきたといいます。
子ども
「すごく緊張してて、練習通りに踊れたらいいかなって思っています」
参加者
「やっぱり、それは存続していきたいという気持ちで、今回も思いましたね」

参加者
「太鼓の次が鉦ね。で、後、踊り」
4月14日、本番の日を迎えました。甲冑姿なども見え、まるで時代行列のようです。