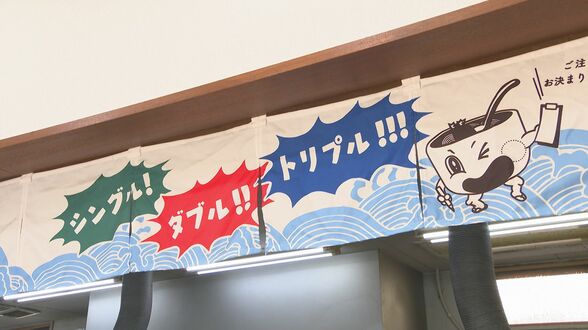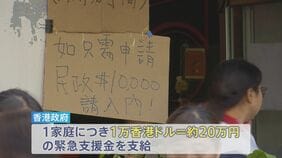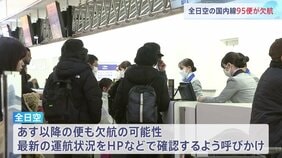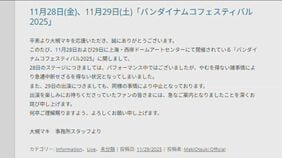新幹線は地方活性化にひと役買っているというデータもあります。九州経済調査協会によると、おととし9月に開業した、長崎市と佐賀県武雄市を結ぶ西九州新幹線では、長崎県と佐賀県での経済波及効果は、駅周辺の再開発やインフラなどの公共投資、宿泊施設の建設費などで、およそ1736億円にのぼっています。
また、日本政策投資銀行の調査では、9年前に石川県金沢市まで延伸した北陸新幹線でも、開業の1年後の経済波及効果はおよそ678億円という推計が出ています。

開業まで30年以上、「並行在来線」は赤字経営続き課題は山積
しかし、実現へのハードルは低くはありません。東九州新幹線は1973年、「基本計画路線」に位置付けられました。実現には開業が前提となる「整備計画路線」へと国に格上げしてもらう必要があり、1月、佐藤知事や宮崎県の河野知事らが国交省を訪れ、要望しています。しかし、決定したとしても開業できるまでには、かなりの時間を要します。北海道新幹線は32年、西九州新幹線は35年もかかっています。
(安部記者)「新幹線ができて良いことばかりではありません。並行して運行されている在来線が、JRから経営分離される可能性があるのです」
避けては通れないのが「並行在来線」の問題です。過去の例では新幹線の開業によって、JRは採算が見込めない路線や、区間の運営を切り離す傾向にあります。例えば、九州新幹線が開業した熊本の「八代駅」から鹿児島の「川内駅」間の在来線『肥薩おれんじ鉄道』は沿線の自治体が中心となって出資した第3セクターが運営を引き継ぎました。しかし、特急列車は廃止、普通列車の運行本数も減るなどして赤字経営が続いています。

この問題は日田市の住民説明会でも不安視する声が上がりました。
(地元住民)「圧倒的にヒト・モノ・カネを動かしているのは車社会で、経営分離して地元負担となると、道路がいいのか? 新幹線がいいのか? そこは不安がある」
県はこうした負の側面も踏まえた上で、東九州新幹線について県民とともに十分に考えていきたいと話します。
(県交通政策課・後藤孝一郎さん)「さまざまな課題も含め、県民の理解と機運の醸成が不可欠で、今後の整備計画路線の格上げの議論に東九州新幹線が遅れることのないよう、議論を重ねていきたい」
期待の一方で課題もある東九州新幹線。県は今後2つのルート案の沿線を中心に住民説明会を重ねる予定です。