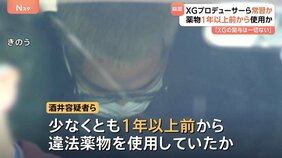77年目の終戦の日を前に「NO WARプロジェクトつなぐ、つながる」、戦争を語り継ぐ意義や大切さについてお伝えします。9日は長年、子どもたちに朗読劇で戦争の悲惨さを語りかけ、平和の尊さを伝える地域グループの思いに迫ります。
8月5日、広島の原爆の日を前に大分市の稙田西中学校では戦争や平和について考える特別授業が行われました。生徒たちは長崎を舞台にした朗読劇の動画を鑑賞し真剣な表情で戦争の悲惨さを学んでいました。
(生徒)「原爆は一瞬の出来事だったけど、傷が残るのは一生だったから、絶対に戦争を起こしてはいけないと思いました。」「経験したことを語れる人が少なくなってきているので、そういうのを自分たちが下の世代に伝えてきたい」
生徒も読み手として参加した今回の朗読劇。上演の主体となったのは地域で25年にわたって活動を続ける「ぽけっとの会」です。
週に2回、小学校の一室で読み語りの練習をする「ぽけっとの会」。これまで県内の小中学校で広島・長崎・沖縄をテーマにした平和朗読劇を行ってきました。現在8人が所属する会の代表を務めるのは篠永朋子さん(79)です。
(ぽけっとの会主宰・篠永朋子さん)「平和朗読をすることによって大昔のことを大昔の人たちが自分の経験のように話してくれる。(子どもたちは)私たちのやっていることを受け止めて、自分の中に落としていっているんじゃないかなって」
篠永さんは終戦時2歳でその記憶はかすかなものとなっています。そのため、当初は戦争について語ることに抵抗があったといいます。しかし、朗読劇を通して戦争を知らない若い世代に伝えていくことの大切さを感じています。
(篠永朋子さん)「子どもたちは『私たちが伝えていかないといけない』って言っているんですよね。だからその子たちが伝えてくれるんであれば、私のできることは戦争のその情景を知っている一人として、がんばって伝えていきたいと思っています」
終戦から77年目の2022年、ロシアのウクライナ侵攻で戦争がより現実のものとなる中、次の世代へ語り継ぐ大切さがいっそう重みを増しています。
全国のトップニュース
高市総理側が自民の当選全議員に数万円相当カタログギフト配布 「お祝い」と説明 党内には「あまりに軽率」受け取り拒否した議員も【news23】

カンボジア首都で日本人15人拘束 特殊詐欺に関与か 大使館へ保護求める駆け込みも増加

中国「日本の再軍事化抑止」と制裁強化 日本の20企業などを“輸出規制”対象に 軍民両用品の輸出を禁止

【今後の雨や雪は?】あす25日は関東など太平洋側で通勤通学の時間帯に雨脚強まるか “バケツをひっくり返したような”激しい雨の所も?【3時間ごとのシミュレーション・24日午後9時更新】

トランプ政権がイランへの攻撃を検討 中東に米艦艇結集 両国の協議は26日…“これが最後のチャンス”か 日本への影響も【news23】

「刃物を振り回している人がいる」JR川崎駅で男性が女にカッターナイフで切りつけられる 自称アルバイトの43歳女を逮捕 電車を降りた際にトラブルか 容疑を否認

【速報】検察側が「無期懲役」求刑 大津市保護司殺害事件 担当保護司を斧やナイフで殺害した罪に問われた36歳男の裁判
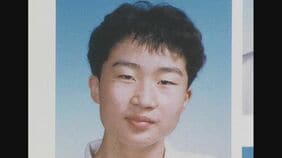
「XGの関与は一切ない」プロデューサーらの逮捕を受けXG公式SNSに投稿 「SIMON」こと酒井じゅんほ容疑者らはコカインなど常習的に使用か