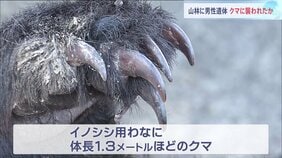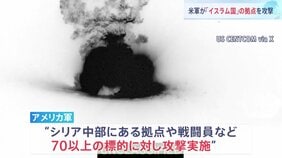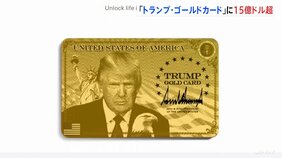13日夜に宮崎県内で最大震度5弱を観測した地震に伴い、気象庁は2回目となる「南海トラフ地震臨時情報」を発表し、関連性を調査しました。
「南海トラフ臨時情報」の制度設計にも携わった名古屋大学の福和伸夫名誉教授に話を聞きます。(聞き手:川野武文アナウンサー、加藤沙知アナウンサー)
(川野武文アナウンサー)
今回、2回目の南海トラフ地震臨時情報が発表されましたが、専門家による評価の結果、8月の地震で出された「巨大地震注意」とは異なり、「調査終了」と発表されました。これにはどのような経緯があるのでしょうか?

(名古屋大学・福和伸夫名誉教授)
これは地震の規模によって、発表する情報を区分けしています。昨年の8月8日の地震は、気象庁のマグニチュードが7.1。もう少し大きな地震で正確にマグニチュードが評価できるモーメントマグニチュードで7.0でした。
「巨大地震注意」という情報は、モーメントマグニチュードが7.0以上のときに発表するというルールになっていて、一方で、昨日の地震はモーメントマグニチュードは6.7だったことで、巨大地震注意に相当する地震規模ではないということで調査終了となったわけです。
元々「調査中」ということを発表するときのマグニチュード、これは気象庁マグニチュードなのですが、閾値はマグニチュード6.8です。
前回は気象庁マグニチュード7.1、実は今回は当初は6.9というふうに言われていました。
6.9だったので、調査中という形で検討会を開いて、そこでモーメントマグニチュードを調べてみたら、6.8に至っていなかったので、調査終了となったのですが、改めて気象庁マグニチュードも出し直してみると、6.6だったということですから、前回と比べると、地震規模が小さくて、当初から6.6であったとすると、「臨時情報(調査中)」というものも出なかったはずということになります。
こういったマグニチュードの評価というのは、正確さを期するためには、ある程度推定に時間もかかることから、今回のようなことは、将来も起こりうるだろうとは思います。

(加藤沙知アナウンサー)
評価のポイントなったモーメントマグニチュードはより精度の高い地震の規模を示すもので前回は7.0、今回は6.7でした。大きさ、影響はどのように違いますか?
(名古屋大学・福和伸夫名誉教授)
マグニチュードが0.2違うと、地震のときに放出されるエネルギーというのは、2倍ぐらい違います。0.5ぐらい違うと、5倍以上地震の規模が違います。
ですから、0.5は大した違いじゃないように思うのですが、地震の規模としてはそれなりに違うのです。
「気象庁マグニチュード」というのは、早くに出したいということもあって、揺れの大きさからすぐに推定するものです。
「モーメントマグニチュード」というのは、もう少し地震の規模をしっかりと調べようといういうもので、算出するのにそれなりに時間がかかるということで、検討会で結論付けるのに2時間ぐらいの時間がかかってしまったということになります。
(川野武文アナウンサー)
「調査終了」となった一方、去年に続き、日向灘が震源の地震で臨時情報が発表されたということで不安に感じた県民も多いと思います。
今後、どのように行動したらよいでしょうか。
(名古屋大学・福和伸夫名誉教授)
基本的には地震というのは、何の情報もなく、前触れもなく起こるのが、普通であるというふうに思っておいていただくことが望ましくて、突発して地震が起きたとしても大丈夫なように、日頃の備えをしておくことが最も重要なことだと思います。
地震に対しての備えというのは、基本的には家を強くし、家具をしっかり固定し、揺れたら、津波に被災地になるようなところでは速やかに避難できるような体制を整える。これに尽きるわけです。
ですから、臨時情報が発表されたかどうかというよりは、常にきちんとした地震対策をしておいていただくっていうことを留意していただければと思います。
※MRTテレビ「Check!」1月14日(火)放送分から