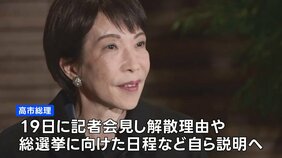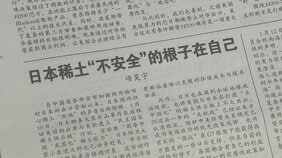記録的寒波で3000世帯以上が断水した石川県輪島市は、5年前にも大規模な断水に見舞われました。市は遠隔でも漏水を確認できる装置の導入を進めていますが、空き家も多く、抜本的な課題解決が難しい状況です。
輪島市は徐々に試験通水を始めていて、市内の宿泊施設では5日ぶりに蛇口から水が流れました。
茅葺庵の山本亮オーナーは「おお!出ましたね。やっぱりほっとします。ずっと山水をくんでいたので、こっちからも出ると安心します」と話していました。
施設では5年前にも1週間にわたって断水が続きましたが、その後、遠隔で漏水を確認できる「スマートメーター」を導入。今回の断水では、メーターを確認した市から施設に連絡がありました。

山本亮オーナーは「ちゃんと異常を検知して、市から連絡が来るという体制ができたのが、安心できる材料だった」と話します。
輪島市は中心部から徐々に水の供給を再開していますが、30日午後5時時点で1426世帯で断水が続いていて、全面復旧のめどは立っていません。
市内では30日も、水道の検針員らが雪をかき分けながら、1軒ずつメーターを確かめ、漏水がないかチェックしていきました。
水道の検針員は「いつも1時間ちょっとかかる所が、きのうは3時間くらいかかった。やっぱり空き家が多い」と話していました。
市は、特に空き家の管理が難しく、漏水の確認に時間がかかると指摘します。輪島市上下水道局の登岸浩局長は「(水道管の)被覆もそうだが、水道メーターの場所を把握するのが一番大事。各家庭の方も常にそういう意識を持ってもらって、メーターボックスの除雪をしてもらえれば作業も進む」と呼びかけます。
市は国の事業を活用してスマートメーターの導入を進めていますが、全体の1割程度にとどまっているのが現状で、増え続ける空き家の管理の難しさが浮き彫りになっています。
寒冷地に比べ凍結対策乏しく 「半空き家」の管理重要に
災害時のライフラインに詳しい金沢大学の宮島昌克名誉教授は、人が住んでいない空き家や、週末やお盆・正月にだけ使われるいわゆる「半空き家」で水道管が老朽化し、漏水が相次いだことが最大の原因だと指摘します。
また、北海道などの寒冷地と比べて、石川県ではあらかじめ水を抜く「水抜き栓」がなかったり、水道管が地中の浅いところに設置されていて、凍結対策が乏しいといいます。
宮島名誉教授は、数年に一度しか凍結被害がない石川県でこうしたハード面の対策を普及させるのは難しいとして、寒波の前に、特に半空き家などの水をあらかじめ止めるなど、住民や自治体が一体となった対策が重要だと呼びかけています。