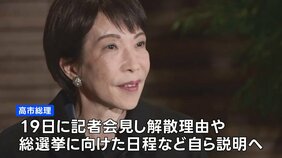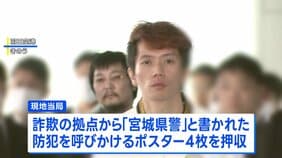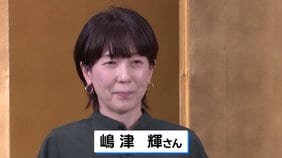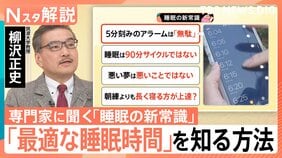石川県能登地方で古くから作られる「いしる」。魚介類を塩漬けにして発酵、熟成させた魚醤で、日本を代表する三大魚醤のひとつです。国の文化審議会は、この「いしる」の製造技術を登録無形民俗文化財とするよう、20日、文部科学大臣に答申しました。

カネイシ 新谷伸一社長「これが仕込みの中のものなんですけど…」
石川県能登町小木で長年、いしるの製造を手掛ける水産物加工会社のカネイシ。こちらでは港で水揚げされたスルメイカのワタをいしるの材料として使っています。
カネイシ 新谷伸一社長「率直に一生産者として国の民俗文化財に指定されたということは非常に喜ばしいことですし、これを機会に私どもも含めて、いしる・いしりを生産している生産者のみなさんに改めて脚光が向けば、非常に地域としても喜ばしい」

国の登録無形民俗文化財になる見通しの「いしる」。地域によっては「いしり」とも呼ばれています。イワシやサバ、イカの内臓を塩漬けにし、1年以上かけて発酵させた魚醤で、秋田県の「しょっつる」などとともに、地域の食文化として受け継がれてきた貴重な発酵調味料です。
大豆を主な原料とする醤油が普及するまでは、能登ならではの調味料として広く親しまれ、今でも煮物などの味付けに使われています。
カネイシ 新谷伸一社長「下に見えている黒い部分がいしるの原液」
おととしには、地元の民宿などが中心となって生産者協議会が発足。いしるを使った料理を提供し、能登ならではの食文化の発信にも努めています。
カネイシ 新谷伸一社長「需要の方は着実に増えていて、とは言っても商品として仕上がるには時間がかかる製品なので、できるだけそういった需要に応えるように着実にいしる作りを行っていきたい」

文化審議会は、「いしる」の製造技術や製造法が発酵調味料の歴史などを今に伝える貴重な食文化と評価。正式に決まれば、石川県内初の国の登録無形民俗文化財となります。貴重な地域の食文化のさらなる発信へ、生産者らの期待が高まっています。