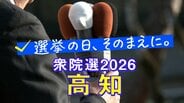地球温暖化対策として、世界中の国や企業が推進する脱炭素化。人口3200人ほどの町、高知県梼原町は、26年後、2050年に再生可能エネルギーによる電力自給率100%を目指してさまざまな取り組みを進めています。先日、町の担当者たちが先進的な取り組みが進むドイツを視察しました。からふるでは、その模様を同行取材し、13日から3日間特集でお伝えします。初日の13日は、“先進国ドイツに学ぶ、脱炭素社会の実現“です。

雲の上の町、高知県梼原町。町の面積の91%を森林が占める小さな町は、その豊かな自然を生かし、環境に配慮した取り組みを積極的に進めてきました。公共施設や住宅の屋根には太陽光発電が。川の高低差を利用した小水力発電で生まれた電気は、学校や、町内の街灯の照明に使用されています。去年8月には四国カルストの風車が生まれ変わり、町の新たなシンボルとして、クリーンなエネルギーを生み出しています。

そんな梼原町がいま、挑戦しようとしているのが「木質バイオマス発電」です。
(梼原町環境整備課 石川智也 副課長)
「だいたいこの辺りを中心に建設をしていこうかと考えています」

温泉や温水プールがある太郎川地区に発電所を建設。木材として利用できなかった木から生産する燃料の「ペレット」を使って発電し、町内へ供給しようとしているのです。しかし現在、国内でペレットによる発電を行っているのは岐阜県高山市や愛媛県内子町など数か所のみ。そこで梼原町の職員らは発電する際に発生する熱の利用方法や、運営の仕組みなどについて学ぼうと、先月ペレット発電による地域づくりの先進国ドイツへと向かいました。
(梼原町環境整備課 石川智也 副課長)
「国内の発電機もいくつか視察したがそこで見切れなかった部分をしっかり確認してきたい」

日本からドイツまでは直線距離でおよそ9000キロ。14時間ほどかけて、南ドイツのミュンヘン空港を目指します。
ドイツの人口は日本のおよそ7割、8500万人ほど。(2023年6月独連邦統計庁)国の面積は日本とほぼ変わらず、オランダ、ベルギー、フランスなど、9か国と国境を接する世界有数の貿易大国です。

(リポート:村山まや)
「1月のドイツは1年で最も寒い時期を迎えます。日中は氷点下、雪が降る日も多く、辺り一面はご覧のとおり銀世界が広がっています」


ドイツには、旧市街地と呼ばれる伝統的なドイツの街並みが残る地区が多くあります。こちらはベルヒングの旧市街地。かつて、戦いから地域の住民を守るために築いた塀に囲まれていて、門を抜けると、まるで絵本の中のようなカラフルでかわいらしい建物が立ち並んでいます。外の地域とを結ぶ門は“グリーディンガートワ”と呼ばれ、1350年ごろにつくられたものだといいます。

(リポート:村山まや)
「時刻は今午後6時半を過ぎたところです。気温はマイナス3℃ととても寒いんですが旧市街地にはご覧のとおりあかりが灯り、昼間とはまた違う温かい雰囲気に包まれています」

1100年以上の歴史を誇るというこの旧市街地は、第二次世界大戦による戦禍を免れたため、街全体に中世の面影を残す、ドイツ国内でもめずらしい場所です。

ドイツはいま、脱炭素化に本気で取り組んでいます。世界の目標より5年前倒しの2045年に“温室効果ガスの排出量実質ゼロ“を達成するため、国を挙げてエネルギーの転換を図っていて、温室効果ガスの削減目標や、再生可能エネルギーの導入について法整備が進んでいます。

南ドイツの町、ミュールハウゼンにあるブルクハルト社です。1879年に創業し、配管の製造などを行っていて、20年ほど前、ドイツでFIT(フィット)=再生可能エネルギーの固定価格買取制度が始まったことをきっかけにペレットやチップといった木質バイオマス燃料をガス化し、発電と熱供給を行う設備を開発・販売しています。

現在は、日本でも40基が稼働していて、梼原町もこの設備を導入します。施設を案内するのは、ブルクハルト社の日本総代理店の担当者、クラウディウス・デッケルトさん。設備はもちろん、ドイツのエネルギー事情にも精通しています。

(ブルクハルト社の日本総代理店担当者 クラウディウス・デッケルトさん)
「ドイツでFITの単価が昔に比べてだいぶ安くなっている。それと同時にウクライナの戦争とかいろいろな影響があって電気代がだいぶ上がっている。エネルギー価格全部上がっている。最近はFITで売電するよりは民間企業に売るか、自家消費したほうが経済的」
長年、風力や小水力での発電を行ってきた梼原町。安定した発電を継続するためには、初動対応や日常管理の大切さが重要だとわかっているからこそ、メンテナンス面も入念に確認します。

(梼原町環境整備課 石川智也 副課長)
「これまでの不具合の情報とかは…」
(デッケルトさん)
「もちろん全部遠隔操作で全部モニタリングしてます。ケーブル関係も自社のシステムを作りたいのでケーブルそのものは外から買っているが制御盤は自社で作っています」
今回の視察には町職員だけでなく、再生可能エネルギー推進のための協議会のメンバーも同行し、こうした点を重点的に確認していました。
(梼原町再生可能エネルギー推進協議会 森山健二 委員)
「すべて部品は作っていることが実際に見れたので、発電機をメンテナンスしている状況も見たが作ってメンテナンスもしている、一貫して製品に対して責任を持ってやってるというのが視察で分かった」
梼原町がブルクハルト社の発電機を導入する大きな理由の一つには、“町内で生産するペレットを使って、効率的に発電できる”という点があります。
(梼原町環境整備課 石川智也 副課長)
「うちはペレット工場があるのでそのペレットの品質を高めて自分のところの発電所で発電して、地産地消でやっていきたいと思っているので」

去年4月、原子力発電を完全に停止したドイツは、現在、電力のほぼ半分を再生可能エネルギーでまかなっています。なかでも木質バイオマス発電は、小さな村やコミュニティで導入され、地域の中でエネルギーを循環させる仕組みが広がってきているといいます。

一方、日本は人口一人当たりの木材の量はドイツのおよそ2.5倍。豊富な森林資源をいかして脱炭素化を進めていける大きな可能性を秘めているとも言えます。
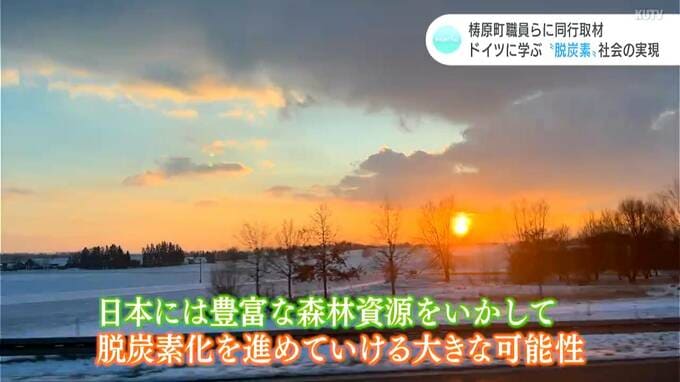
(デッケルトさん)
「まさに木が多い地域が木質バイオマスを積極的に使うと再エネ利用にもなるし脱炭素にもなる、いい意味で地産地消にもなる。林業にもお金が回るし、発電や温水を使うところにもメリットが生まれる。地産地消、地域循環という意味では梼原町にとってもプラスが生まれると思う」