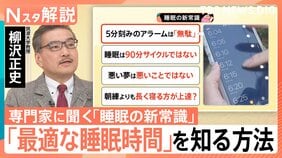「災害時、観光客の命をどう守るか」です。東日本大震災で被災したホテルの従業員らが高知県内の観光関係者に、災害時の宿泊施設の役割や初動対応などを講演しました。
高知市で開かれたこの講演会は高知県が観光業の関係者らに災害発生時の対応などについて考えてもらおうと毎年開催しています。24日は宮城県南三陸町のホテルでおかみを務める阿部憲子(あべ・のりこ)さんと観光危機管理の研究者 高松正人(たかまつ・まさと)さんが登壇。それぞれの経験や知識を踏まえて災害が起きた際の宿泊施設の役割や初動対応について話しました。
東日本大震災の前から「避難所としてのホテル」を意識していた阿部さん。発災後は実際に避難者を受け入れ、心のケアとして交流の場も作ってきました。さらに復興に向けた動きの中でも宿泊施設は大きな役割を果たすと訴えかけました。

(南三陸ホテル観洋 阿部憲子さん)
「衣食住を提供する場ということは災害のときに頼られる。ライフラインを復旧する工事の関係者や研究者そういう方も泊まって拠点にする場所がないといろいろなことが進まないので、社会的にも認められる産業になりたいと願いながら声を上げて伝えている」
観光危機管理を研究する高松正人さんは発災後に客の安全を確認したり避難させたりする際の注意点や、呼びかけに使える具体的なフレーズなどを紹介しました。
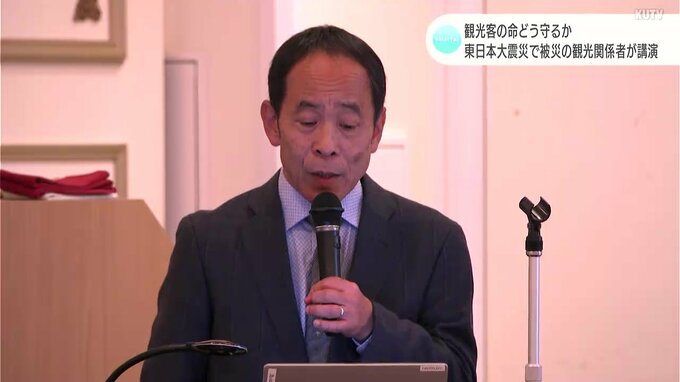
(観光レジリエンス研究所 高松正人 代表)
「『この方を手伝ってあげてください』『一人では歩けないから肩を貸してあげてください』ふだん訓練の中でこういう表現をしておかないと、なかなか(本番でも)できないこういう風に言われると非常時には人は動く」
(参加者)
「サービス業なのでふだんは丁寧な言葉を使っているが、緊急時にはそんなことを言っている場合じゃないと言われて目からうろこだった。講演を聞いていなかったら実際のときも危機感なく言ってしまっていたと思う」
「顧客に観光業の人がいるので、できることを提案できたら」
観光客の命をどう守っていくか。参加者たちにとって災害時の対応を改めて考え直すきっかけとなったようです。