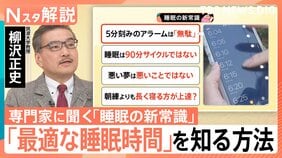能登半島地震の被災地で捜索、救助活動を行った高知県警の広域緊急援助隊が現地での活動内容を報告しました。多くの住宅が倒壊していた現状を目の当たりにした隊員が伝えたいこととは。
県警の広域緊急援助隊は大規模な災害が発生あるいは予想される場合に派遣される部隊で、機動隊の現役隊員や元隊員を中心に組織されています。元日に発生した能登半島地震を受けて高知から25人の隊員が石川に入り、5日から輪島市内で要救助者の捜索・救助にあたりました。

今回活動を行った現場は二か所。1つめの現場は山間部で倒木によって半壊した住宅です。
(県警広域緊急援助隊 大畠翔 隊員)
「関係者からの聴取の結果や民間団体の救助犬による探知の結果、この家に要救助者がいる可能性が非常に高いと判断したため活動を実施した」
もともと2階建てだった住宅は長さ2、30メートルの木が2本倒れてきたことで倒壊し1階部分が潰れていました。

(県警広域緊急援助隊 中澤公貴 分隊長)
「1階に居住していた可能性が極めて高いとの情報を得たので、その真上の部屋の2階の床部分をチェーンソーで切断して細いカメラで中を確認したところ要救助者を発見した」
懸命な救助活動を行いましたが発見された要救助者はすでに亡くなっていたということです。
(県警広域緊急援助隊 中澤公貴 分隊長)
「もう少しでも早く救出できていたら命が助かっていたのかなという心境、その気持ちに尽きる」
もう一つの現場では自衛隊や大阪府警の部隊と協力し全壊した家屋の下敷きになった遺体を搬出しました。

(県警広域緊急援助隊 中澤公貴 分隊長)
「要救助者の背中に直径4~50センチの梁が乗っていてその梁をチェーンソーで切断しようかと思ったのですが、切断してしまうと家屋同士が繋がっていて隊員が入るスペースに落ちてくる危険性があったので梁をリフトアップして除圧することで救出した」
派遣期間中は大雪や落雷、さらに度重なる余震にも見舞われたという隊員たち。被災地の現状を目の当たりにし、南海トラフ地震に向けて改めて対策を呼びかけたいと感じた点が多くありました。

(県警広域緊急援助隊 中澤公貴 分隊長)
「家財道具の固定化は必要だと思った。少しの揺れでも倒れる可能性があるので。今回の災害のように支援物資がなかなか届かない事が予想されるので、各家庭でも(備蓄品を)用意しておいて支援が来るまで生活することが大切だと思った」

「我々も県内で災害が発生した際は迅速に災害救助活動ができるように、これからも日々の訓練を怠らず有事に備えて消防や自衛隊との横のつながりも大切にして連携をとってこれからも訓練にあたっていきたい」