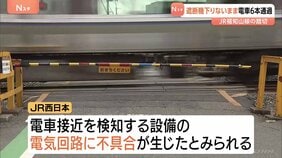太平洋戦争は、終わった後も様々な悲劇を生みましたが「シベリア抑留」もそのひとつです。
80年が経った今も、実態がわからない、このシベリア抑留を研究したいとロシアから札幌市にやってきた留学生を取材しました。
■「なぜ日本人がここで…」ロシア人学生が向き合うシベリア抑留
東京・永田町。

鈴木宗男 参院議員
「筆舌に尽くしがたい苦労があった」
小池晃 参院議員
「政府が、国会が手をこまねいているわけにはいかない」
シベリアなどで強制労働をさせられた元抑留者や支援者が、国会内で集会を開きました。
その中に、札幌で学ぶ、ロシア人留学生の姿がありました。

北海道大学文学院 ビコーニャ・アリナさん(24)
「シベリア抑留はまだ忘れられていない。そして沈黙の歴史にならなかったということです」
ビコーニャ・アリナさん。4月から北海道大学の大学院に通っています。
アリナさん
「抑留者の帰国後の生活はあまり明らかになっていない」
専門は「シベリア抑留」の研究。太平洋戦争の終結後、旧ソビエトによって、およそ60万人の日本兵や民間人が、極東からヨーロッパに設けられた、ラーゲリと呼ばれる=強制収容所に抑留。過酷な労働を強いられました。
アリナさん
「ナホトカ市出身なので、この地域は昔から日本との歴史的経済的、社会的な関係が深かった」
アリナさんが生まれ育ったのは、ロシア極東の港湾都市=ナホトカ。
冬でも凍らない港があり、物流の拠点として栄えました。
小樽市や京都の舞鶴市と姉妹都市で、日本にとっても身近なマチ。
そして、シベリア抑留の強制収容所や帰還船の出発地でもあります。

アリナさん
「元々の抑留者の墓地が建っていて、なぜ日本人がここにいたのか、なぜこの方がここで亡くなったのかという質問にどんどん答えを探っていってシベリア抑留の研究に至りました」
ウラジオストク極東連邦大学でも、シベリア抑留の歴史や体験者のトラウマなどを研究していたアリナさん。
「抑留体験者に直接話を聞きたい」留学先に選んだのが、札幌でした。