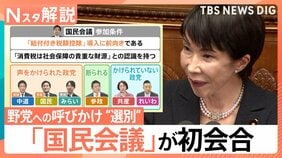現在の東京大学が広大な土地を購入…

(道マニア・石井あつこさん)
「明治の初期は、もともと大滝村(現在の秩父市)の村有林だった。それを、当時の東京帝国大学(現在の東京大学)が広大な土地を購入した。林業や森林資源の研究、財産の確保という目的があったと思う。それが東京大学演習林の始まり」
大正5年、森林資源の確保や林業の研究を行うために東京大学が創設した「秩父演習林」。大正12年に伐採した木材を搬出するための鉄道の建設が決まると、その工事は小森川沿いで森林鉄道を管理していた民間会社が請け負いました。

工事開始6年後の昭和4年、2.5kmの軌道が敷設され、徐々に木材の搬出が行われるようになります。その後も延伸工事が進み、昭和11年に全長約6kmの入川森林軌道が完成。40年にわたって稼働を続けてきましたが、昭和44年、伐採可能な樹木の枯渇と国道の建設により廃線となりました。
(道マニア・石井あつこさん)
「森林鉄道は北海道から沖縄まで1000路線、8000kmはあったとされる。斫伐(しゃくばつ)した木材を運ぶのが主たる目的であるのは間違いないが、集落があれば物資を運んだり、林業で集落が栄えて学校ができれば通学路として利用されたりもした。山に住む人達の拠り所になっていたと思う。運び出された資源は様々な用途に使われて、日本の近代化を根底から支えていた」