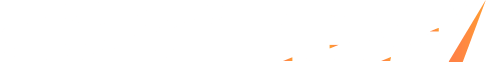「今夜、我が家に食事に来ないか?」
ここでも、ロシア語は効力を発揮する。ソ連兵の言葉を明確に理解できたことで、仕事の飲み込みも早かったし、周りの日本兵への指示も的確だった。
中隊長となり、自動車整備工場でも頭角を現した春男さんは、ソ連兵にも気に入られた。そんなある日、春男さんは工場長に声をかけられた。それは、捕虜の身としては信じられない言葉だった。
「今夜、我が家に食事に来ないか?」
当時、日本兵は捕虜として、早朝に不十分な食事を済ませ、日が暮れるまで強制労働を余儀なくされ、満足な食事も与えられず、空腹の中で眠りにつくのが日常だった。炭鉱や工場を往復するだけの単調な日々の連続、そんな自分が工場長に招待を受けたのだ。困惑したのも無理もなかった。

知人の自宅を訪ねるなど、いつ以来だろうか。関東軍として満州からシベリアへと連行され、捕虜として捕らわれの身になってからは、銃をツルハシに代え、耐え難き屈辱や矛盾も受け入れてきた。春男さんは相手が誰であろうと、長年得られなかった自由を感じていた。
雪に覆われた大地は、まるで静寂の中で眠っているかのようだった。その静けさの
中、雪を踏みしめる音と自分の吐く息だけが聞こえてくる。暗闇の中で灯りが見えた。工場長の自宅は木造のロッジ風の建物だった。ペチカから繋がる煙突からは、白い煙がゆっくりと立ち昇り、夜空に溶け込んでいた。