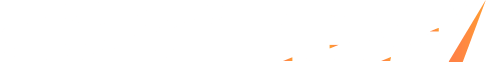忘れられないターニャの手料理
春男さんはドアをノックすると、工場長と夫人が「よく来てくれたね」と笑顔で迎えてくれた。その顔は、普段自動車整備工場では見せない柔和な表情だった。
「工場では、長として厳しい顔をしていても、家庭で見せる顔は違うものなんだ」
春男さんはロシア人も、日本人も人間の本質は同じなのかもしれないと感じた。
扉の向こうから若い女性が顔を出してきた。
「いらっしゃい、ハルオ」
春男さんの憧れの人、ターニャその人だった。工場長のひとり娘のターニャもまた、職場の顔とは違うリラックスした表情で出迎えてくれた。彼女のプライベートな一面を垣間見たような気がした。
やや使い古した感のあるテーブルの上は、すぐにご馳走で彩られた。その中で、決して忘れられない味があった。ターニャの手料理のボルシチたった。

やや酸味のある香りが鼻腔を刺激したのか、食欲が増した。空腹に耐えかねた胃袋がお待ちかねだった。スープにスプーンを入れ、口に含むと、その美味しさが口の中で広がった。ビーツの深紅の色が鮮明なスープに、様々な具材が入っていた。
トマト風味で、それぞれの野菜の甘みが溶け込んでいたが何が入っていたかは覚えていないという。会話もそこそこに夢中になってボルシチを食べた。