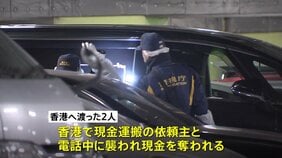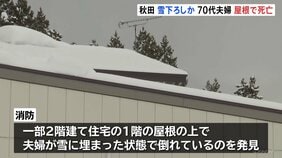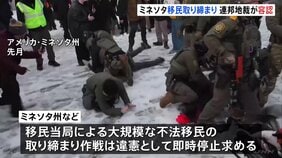新潟大学で液状化現象を研究している保坂吉則助教が注目したのは、地震の“揺れの大きさ”の違いです。

新潟市中央区と西区の震度計では同じ「震度5強」の揺れが、元日の能登半島地震で観測されていました。
しかし、気象庁が実際に観測された震度などから震度計のない場所の震度を推計した『推計震度分布図』では違いが出ていたのです。

それによりますと、新潟市中央区の信濃川沿いでは主に「震度4」だったと推定される一方で、「震度5強」と推測される地域の広がる西区では、中でも、JR寺尾駅付近や坂井東などでは「震度6弱」の揺れだったとされているのです。
【新潟大学 保坂吉則助教】
「震度5強だと液状化するっていうのはよく聞きますので、その辺が今回のボーダーだったのかなって思います」

それでは、中央区と西区で揺れの大きさが違ったとすれば、その“差”はなぜ生まれたのでしょうか?